
投資用マンションの運用では、家賃収入がしっかり入っているのに「手残りが全然増えない」「毎月ほとんど残らない」という悩みを抱えるオーナーが少なくありません。
表面利回りは良く見えても、実際の収支は管理費・修繕積立金の増加、家賃の下落、空室期間、設備の故障など複数の要因が重なって圧迫されやすい構造になっています。
手残りが減ってきたのは、運用が失敗したからではなく、“見直すべきポイントが積み上がってきたサイン” であることがほとんどです。
この記事では、手残りが減る理由をわかりやすく整理し、改善策と売却の判断基準、そして最終的に「いくら手元に残るのか」を最大化するための視点をまとめます。
不動産投資は、数字と状況を冷静に整えることで、無駄な損失を防ぎながら次の選択がしやすくなります。ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
\オークション査定で高値売却を実現/
複数の不動産会社が同時に入札する「オークション形式」で、最も高い査定を提示した会社をご紹介します。営業電話もなく、スムーズに比較検討できる安心の仕組みです。
「損をせずに手放したい」「信頼できる会社に任せたい」という方は、まずは無料査定からお試しください。
ReTrueの無料査定を試す
投資用マンションの運用で「手残りがほとんど残らない」と感じる場面は、多くのオーナーに共通しています。
見かけの利回りは良くても、実際の収支となると数字が思うように残らないケースは珍しくありません。
収支悪化の原因は一つではなく、支出の増加・収入の低下・突発的な費用が複合的に重なることで起こります。ここでは主な悪化の原因についてご紹介します。
管理費や修繕積立金は、築年数の経過とともに上昇する傾向があります。
特に修繕積立金は大規模修繕に備えるため、管理組合の判断で見直しが入ることが多く、築20年を超えるマンションでは倍額近くになるケースも見られます。
たとえば、築浅時は6,000円だった積立金が築20年で12,000円に上がると、年間で72,000円の支出増となり、月の手残りを確実に圧迫します。
運用の現実として、買った時のコスト構造をそのまま維持できるとは限らない点を理解しておくことが重要です。
管理費の増加も小さくありません。管理会社の人件費や資材費の高騰に影響され、管理費が毎年少しずつ上がる場合があります。
エレベーターや24時間ゴミ対応など共用サービスが充実している物件ほど、上昇幅が大きくなる傾向があるため、自身のマンションの設備構成も確認しておくと支出予測がしやすくなります。
築年数の経過によって家賃は自然に落ちていく傾向がありますが、オーナーの多くは「入居がついているから問題ない」と見過ごしてしまいがちです。
実際には、相場より家賃が高い状態で維持している場合、次の入居付けで一気に3,000〜5,000円下がることもあり、退去のタイミングで収支が大きく悪化します。
たとえば、月額家賃が70,000円から65,000円に下がるだけで年間60,000円の減収となり、管理費の増加と合わせると手残りはさらに細ります。
周辺エリアの新築供給も家賃下落の要因になります。駅徒歩圏で新築が増えると、築古物件は相対的に選ばれにくくなり、空室期間が伸びやすくなります。
家賃下落は緩やかでも、累積すると大きな影響になるため、年に一度は周辺相場と自身の物件の家賃を比較することが大切です。
投資用マンションの収支は「年間家賃収入」が基準になるため、1ヶ月の空室でも利回りが大きく下がります。
たとえば年間家賃84万円の物件で1ヶ月空室になると、収入は77万円に下がり、単純計算で利回りは約8%低下します。
この影響は想像以上に大きく、年に何度も空室が発生する物件では実質利回りが表面利回りを大きく下回ることになります。
空室期間が長引く原因としては、家賃設定が相場より高い、内装が古い、募集条件が周辺物件に比べて弱いなどが考えられます。
また繁忙期である1〜3月を逃すと、4月以降は比較的動きが鈍くなるため、募集戦略のタイミングも重要です。
空室が続く物件は、改善策を講じないと毎年の収支が不安定になり、結果として手残りの減少につながります。
ローン返済額の占める割合が大きい場合、収支が少し崩れただけで手残りがほとんど残らないという状況になりがちです。
特に金利上昇局面では、変動金利のローンを利用しているオーナーは返済額が増えるリスクがあります。元利均等返済では、毎月の返済額は一定ですが、元本の減り方は遅いため、初期の数年間は特に手残りが少ない構造になりがちです。
購入時に「月5,000円でもプラスなら良い」と考えていても、家賃が少し下がるだけで赤字に転じることがあります。
収支の安定性は「返済比率(家賃に対する返済額の割合)」で判断でき、これが高すぎる物件は収支悪化のリスクが高いと言えます。
固定位の費用として、固定資産税・都市計画税・火災保険料などがありますが、これらは年々じわじわと増える傾向があります。
特に火災保険料は数年に一度の更新時に大きく値上がりすることがあり、更新のたびに手残りが減ると感じる原因になります。
また、給湯器やエアコンなどの設備交換が必要になると10万円〜20万円の出費が発生し、単月の収支が大きく悪化します。
1R・1Kタイプでも設備の老朽化は避けられず、築20年を超えると突発的な修繕の可能性が高まります。こうした一回の費用が年間収支を大きく損なうため、長期的な費用計画が必要です。

投資用マンションの収支が崩れ始める物件には、いくつかの共通点があります。
手残りが減ってきた原因を深掘りすると、物件そのものの競争力や管理体制に問題があるケースが多く、放置するほど収支へのダメージは大きくなります。
早い段階で兆候をつかむことで、改善策や売却判断をスムーズに行うことができ、結果として資産価値の下落も抑えやすくなります。
築年数が20年を超えると、給湯器やエアコン、インターホンなど主要設備の故障が増え、入居者の入れ替わりごとに修繕費がかさむ傾向があります。
設備が古い状態のままでは内見時の印象が弱く、空室期間が長引く原因にもなります。たとえば給湯器の交換だけで10万円前後の負担が発生し、年間収支が一気に悪化することもあります。
築古物件では「突発費用の発生確率が高い」という前提で見ておくことが大切です。
設備更新がされていないマンションは、家賃が相場より高く維持されにくく、募集条件でも不利になります。
早期に確認するためには、入居者退去のたびに室内の設備年次と状態をチェックし、必要な更新がどの程度残っているか可視化しておくと判断しやすくなります。
家賃が相場より高いままだと、内見数が伸びず、空室期間が長引きがちです。
特に管理会社任せで募集をしている場合、相場変動を反映できないまま数年経過し、家賃のズレが大きくなるケースがあります。
たとえば同じマンションタイプで周辺相場が70,000円なのに、自身の物件が75,000円で募集されていると、1〜2ヶ月の空室延長は容易に起こり得ます。
相場とのズレを早期に発見するには、年に1回は周辺の類似物件を3〜5件以上比較することが有効です。
また、SUUMOやHOME’Sなどで条件検索を行い、同程度の築年数・駅距離と比べて妥当な価格帯になっているか確認すると、家賃調整の必要性がわかりやすくなります。
管理会社の動きが鈍いと、オーナーの収支にそのまま影響してしまいます。
報告が遅れる、家賃設定の見直し提案がない、広告掲載が少ないといった状況では、募集のスピードが落ちやすく、結果として空室期間が長引いてしまいます。さらに、入居者対応が後手に回ると満足度が低下し、早期退去につながるケースもあります。
管理体制に不安を感じるサインとしては、募集状況の共有が月1回以下しかない、内見数や問い合わせ数の報告がない、競合物件との比較資料が提示されない、といった点が挙げられます。
こうした兆候が見られる場合は、管理会社の見直しを検討するタイミングといえます。
修繕積立金が低く設定されているマンションは、一見すると手残りが多く見えますが、将来的に大規模修繕が近づくと一気に値上げされる可能性が高く、長期的な収支を圧迫します。逆に、過去の修繕履歴が少なく、早い段階で積立金が高額になっているマンションも、オーナーの負担が大きくなります。
早期発見のポイントは、長期修繕計画の確認です。今後の修繕予定が過密である、積立金不足が指摘されている、直近の総会で値上げ議案が検討されているといった情報があれば、収支悪化のサインとして受け取ることができます。
新築マンションが多いエリアでは、築古物件が競争力で劣りやすく、家賃下落と空室期間の長期化につながります。
とくに単身者向けの物件が集中するエリアでは、供給過多によって募集内容が相対的に弱く見えてしまうことがあります。たとえば同じ駅に徒歩圏で新築が複数建つと、築20年前後のマンションは家賃が下がりやすくなります。
供給過多を早期に見つけるには、建設予定物件や新築公開情報を定期的にチェックすることが効果的です。エリアの掲載物件数が急に増えている、競合物件が同じ条件で多く存在する、といった兆候があれば、募集戦略を見直す必要があります。

手残りが減ってきても、すぐに売却へ進む必要はありません。
まずは収支の改善余地があるかを見極め、可能な部分から調整することでキャッシュフローが回復するケースは多くあります。
改善ポイントは「家賃収入を上げる方向」と「支出を抑える方向」の両面に分かれ、物件の状況によって最適な組み合わせが異なります。
ここでは、投資用マンションで実践されやすい具体策をご紹介します。
家賃が相場からずれていると、内見数が伸びず、空室期間が長くなるため、収支の悪化を招きやすくなります。家賃調整は単純に値下げをするだけでなく、募集条件の工夫によって改善できる場合があります。
相場調査の方法としては、SUUMO・HOME’Sなどで自身と同じ条件の物件を検索し、実際の募集家賃を3〜5件比較するのが基本です。
築年数や駅距離が近い物件を基準にすると、適正な募集価格の目安がつかめます。
また、家賃を下げずに競争力を上げたい場合は、敷金・礼金を調整したり、インターネット無料など付帯サービスの導入を検討することで、内見数の増加を狙うことができます。
内装が古いままでは、築年数が近い競合物件に見劣りしてしまい、空室期間を長引かせる要因になります。大規模なリフォームが必要なわけではなく、数万円のミニ改善でも効果が大きいことがあります。
具体例としては、LED照明への交換、アクセントクロスの施工などがあります。これらは2万円〜5万円程度で実施できることが多く、翌月の入居成約につながるケースがあります。退去時の原状回復と合わせて施工できるため、費用対効果の高い改善として検討する価値があります。
管理会社の対応が遅い、募集提案が少ない、広告掲載が不十分といった状況では、空室期間が長くなり、結果としてキャッシュフローに悪影響が出ます。管理会社を変更することで、入居付けのスピードが改善し、収支が回復するケースは珍しくありません。
募集力の弱い管理会社のサインとしては、月次報告がない、内見数の共有が遅い、他社掲載が少ないなどが挙げられます。
管理変更は難しい手続きではなく、一般的には1〜2ヶ月程度で切り替えが可能です。改善余地を見極めるためには、現在の管理状況を一度整理し、管理会社に募集状況の報告書を提出してもらうと、問題点が浮き彫りになります。
支出を減らすことは、少ない負担でキャッシュフローを改善する方法の一つです。
火災保険料は保険会社によって金額に幅があり、更新のタイミングで見直すことが可能です。賃貸保証会社のプランや広告料(AD)の扱いも、管理会社との交渉によって調整できる余地があります。
サブリースに関しては、家賃収入が一定である一方、手残りが少ないというケースが多いため、契約内容の見直しや解除を検討することで収支が改善する場合があります。解除には事前の通知期間が必要なため、早めに契約書を確認しておくと計画が立てやすくなります。
返済額が高く手残りが少ない物件では、借り換えや繰上返済を行うことでキャッシュフローが改善することがあります。
借り換えは金利引き下げの効果が期待でき、毎月の返済額が減る可能性があります。審査や手数料が必要ですが、長期保有を前提とする場合には有効な選択肢です。
繰上返済については、返済比率や家賃下落のスピードを見ながら検討します。たとえば月に1万円しか手残りがない状態でも、50万円〜100万円の繰上返済を行うことで返済が軽くなり、月次収支が改善するケースがあります。
ただし、手元資金を使い過ぎると生活に影響が出るため、余剰資金の範囲で計画的に進めることが重要です。

キャッシュフロー改善策を実行しても、収支が思うように好転しないケースがあります。
これは物件自体の競争力やエリアの構造的な要因が関係していることが多く、オーナーの努力だけでは改善が難しい場合もあります。
こうした状況では、保有・売却の両方を客観的に見直し、最も損失が少ない選択肢を選ぶことが重要です。収支が改善しない状況を放置すると、残債の減り方と家賃下落のバランスが崩れ、時間をかけるほど手残りが減っていく可能性があります。
毎月の手残りが少なくても、大きく赤字にならない範囲であれば、長期保有によってローン残債を減らすという選択があります。
ローンの返済は確実に元本を減らしていくため、数年後に残債が小さくなれば、売却時の手残りが大きくなる可能性があります。たとえば残債があと7年で完済予定の場合、保有を続けることで売却価格との差額が広がり、出口戦略に余裕が生まれることがあります。
ただし長期保有にはリスクもあります。家賃下落が続くエリアでは、追加の空室期間や修繕需要によって、さらに収支が圧迫される可能性があります。
また、築年数が30年以上になると売却価格が大きく低下するケースが多く、長期保有が最適とは言い切れません。長期戦略を選ぶ際は、ローン残高の推移と家賃下落のスピードを数値で比較し、現実的なメリットがあるかを判断することが大切です。
改善しても収支が好転しない場合は、売却によって資産を整理するという選択肢があります。
特にオーナーチェンジ物件は収益不動産としての価値が評価されるため、空室でなければ一定の価格がつきやすい特徴があります。
家賃が市場より少し高い場合でも、入居中であれば価格が下がりにくく、スムーズな売却が期待できます。
空室のまま売ることも可能ですが、募集活動と並行すると時間がかかり、価格交渉が増える傾向があります。空室売却の場合は、家賃設定の見直しや簡易リフォームをしてから売り出すことで、買主が「すぐに運用できる物件」と判断しやすくなるため、価格を維持しやすい流れが作れます。
売却を検討する際は、複数の査定を比較すると数字の精度が高まり、物件の立ち位置が客観的に把握しやすくなります。また、仲介手数料が低い会社を選ぶことで手残り額が増え、資産整理の効果が大きくなります。
手残りがゼロ〜月数千円の状態が続き、改善策を講じても回復しない場合は、赤字に転じる前に売却を検討するタイミングといえます。
赤字になると、ローン返済のために自己資金を補填する必要が生まれ、精神的な負担も大きくなります。こうした状況を避けるためには、売却判断の基準を事前に持っておくことが有効です。
判断基準としては、家賃が3年連続で下落している、空室期間が年1回以上1ヶ月を超える、修繕積立金の大幅値上げが予定されているなどがあります。また、ローン残高と相場価格の差が縮まっている場合は、損失が最小限の状態で出口を確保するチャンスです。
売却は決して後ろ向きな選択ではなく、資産運用全体の最適化に向けた戦略の一つです。保有と売却のどちらが自分にとって有利かを冷静に判断することで、長期的な資産形成にプラスになる選択ができます。
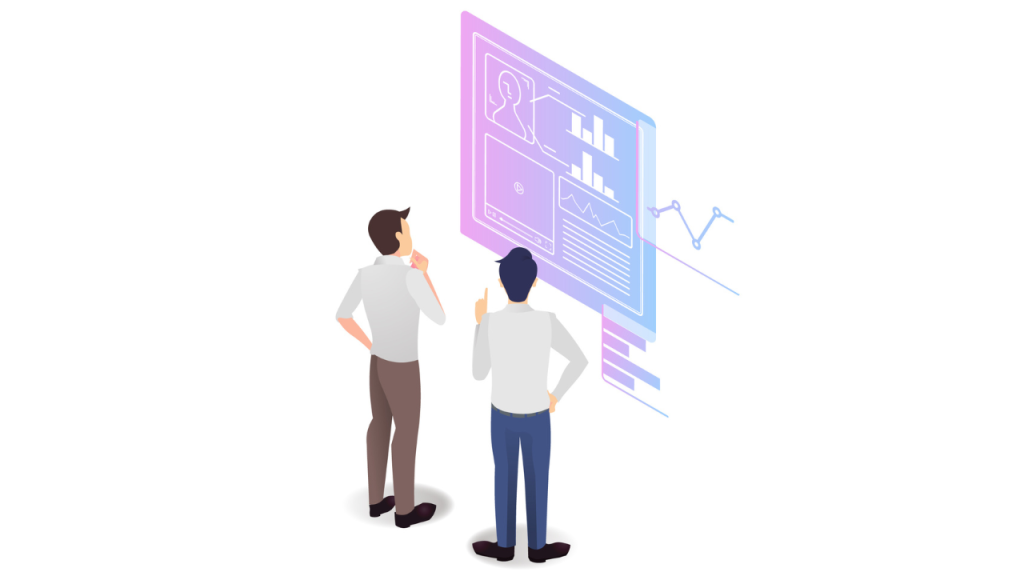
投資用マンションの収支が安定しているときは、売却を考える理由があまりありません。
しかし、さまざまなサインが積み重なると、「いまのまま持ち続けるよりも、売るほうが合理的かもしれない」という局面が訪れます。
ここでは、オーナーが気づきにくい“そろそろ見直しどき”のポイントを整理し、具体的な判断基準として使える形にまとめます。数字や状況の変化をもとに考えることで、感情に左右されず冷静な選択がしやすくなります。
家賃が1年ごとに数千円ずつ下がる状況は、一見すると大きな問題に見えません。しかし累積すると年間収入が確実に減り、手残りを圧迫する大きな要因になります。
家賃が3年連続で下落している、または次の入居付けで明確に相場より安くなる見込みがある場合、収益性の低下が続く傾向にあります。家賃減少は回復しにくいため、早い段階で見直しを検討するべきタイミングです。
空室期間が1ヶ月を超える頻度が増えてきたら、物件の競争力が弱まっているサインです。
募集をしても内見数が伸びない、問い合わせが少ないといった状況は、築年数・設備・家賃設定など複数の要素が影響しています。
以前は1〜2週間で決まっていたのに、最近は1ヶ月以上かかるようになった場合、保有し続けるほど空室のリスクが高まる可能性があります。収支が安定しない状態が続く前に判断する材料となります。
マンション全体の修繕計画で積立金の値上げが決議された場合、毎月の収支は直接的に悪化します。
特に築20年を過ぎる時期は、積立金の増額幅が大きくなることがあり、年間で数万円〜十数万円の負担増になるケースもあります。
値上げが数年続く、あるいは一度に大きく引き上げられる予定がある場合は、将来的な手残り減少を見越して売却を考えるきっかけになります。
管理会社を変更することで空室や家賃の問題が改善するケースはありますが、複数の会社に依頼しても改善が見られない場合は、物件自体の競争力が低下している可能性が高いと言えます。
構造的に収益が上がりにくい状況にあると判断でき、努力での改善が難しいため、売却という選択肢が現実味を帯びてきます。
管理の質ではなく“物件そのもの”が原因の場合は、保有し続けるほど収支が厳しくなる傾向があります。
月5,000円しか残らない状況は、少しの変化で赤字に転じる不安定な状態です。家賃が数千円下がる、管理費が改定される、給湯器が故障するといった小さな出来事だけで、年間収支がマイナスになる可能性があります。
精神的にも「いつ赤字になってもおかしくない」という負担が大きくなりやすく、運用の継続そのものがストレスに感じられることがあります。
ただし、減価償却による節税効果が大きく、トータルでプラスに働いているケースでは事情が異なります。
年間の税負担が軽くなることで、実質的な“手取りベース”では赤字にならない場合もあります。この場合は節税メリットが今後も続くのか、築年数や設備更新のタイミングを踏まえて総合的に判断することが重要です。
いずれにしても、手残りが少ないほど改善の余地は限られてくるため、保有か売却かの見直しを始めるタイミングとして意識しておくと検討がしやすくなります。

投資用マンションを売ると決めた場合、いちばん大きく差が出るのは「いくらで売れるか」ではなく「最終的にいくら手元に残るか」です。
表面の売却価格だけで判断すると、必要な費用や引継ぎ条件を見落としてしまい、結果として手残りが想定より少なくなるケースもあります。
ここでは、オーナーの収益を最大化するために押さえておきたいポイントを整理し、具体的な行動につなげやすい形でまとめます。
売却価格は築年数や相場だけでなく、「売り出す時期」でも変動します。
単身者向け物件は1〜3月の繁忙期に需要が集まりやすく、賃貸付けがしやすいため、空室でも買主が前向きになりやすい特徴があります。
また、金利動向やエリアの再開発など、外部要因で投資家の購入意欲が高まる時期もあります。タイミングを知っておくことで、同じ物件でも数十万円以上手残りが変わることがあります。
投資用マンションは、入居者がいる「オーナーチェンジ物件」のほうが安定収入を評価され、高めの価格がつきやすい傾向があります。
評価の中心になるのは、家賃の水準・入居者属性・滞納の有無・管理状況といった情報で、これらが整っているほど減額されにくくなります。
たとえば相場より家賃が高すぎる場合は、買主が「家賃調整あり」と判断して値下げを求めることが多いため、適正な家賃にチューニングしておくと価格維持につながります。
買主がもっとも不安に感じるのは、「購入後に何が起こるかわからない」という点です。
賃貸借契約書、入居者情報、家賃入金履歴、修繕履歴、管理規約、長期修繕計画などが一式そろっていると、買主は安心して価格を受け入れやすくなります。
資料がそろっていない物件は“運用リスクが高い”と判断されやすく、価格交渉を受けやすくなるため、引き渡し前に資料を整理しておくことが大切です。
売却時の仲介手数料は、条件によっては数十万円〜百万円程度になることがあります。
手残りを増やすための最も直接的な方法は、このコストを抑えることです。仲介手数料無料サービスや成果報酬型の会社を活用すると、売却価格が同じでも最終的な手元に残る金額が大きく変わります。
特に投資用マンションは価格帯が高く、手数料の影響が大きいため、複数社で費用条件を比較する価値があります。
査定価格は会社ごとに差がありますが、数字の高さだけで選ぶと後の価格調整で失敗することがあります。
比較すべきポイントは、査定の根拠、販売戦略、想定される買主層、過去の成約実績などです。特に収益物件の場合は、どの程度の利回りで買主に提示するかによって成約価格が変わるため、根拠が明確な査定を提示する会社ほど信頼性があります。
複数社に査定を依頼し、数字ではなく“戦略”で選ぶことが手残りの最大化に影響します。
投資用マンションの運用で手残りが減ってきたとき、多くのオーナーは「自分の物件だけが悪いのでは」と不安を感じます。
しかし、収支が悪化する背景には必ず理由があり、家賃下落・管理費や積立金の増加・空室期間の長期化・設備故障など、複数の要素が重なって起きているケースがほとんどです。
まずは何が原因で手残りが減っているのかを整理し、改善できる部分がどこにあるのかを見極めることが、最初の一歩になります。
手残りが減ってきた状況は「終わり」ではなく、「立ち止まるべきサイン」です。
数字や状況を一度整理してみることで、改善に動くのか、それとも売却という選択肢を取るのか、より納得のいく判断ができるようになります。
ムリに持ち続けて負担を増やすよりも、早めに方向性を決めるほうが、結果的に資産全体の健全性を守ることにつながります。
売却を検討されている場合は、まず “いくらで売れるのか” を把握することから始めてみてください。
当社では無料でAI査定をご利用いただけますので、価格の目安を知りたい段階でも気軽にお試しいただけます。
売却や運用に関して気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
\オークション査定で高値売却を実現/
複数の不動産会社が同時に入札する「オークション形式」で、最も高い査定を提示した会社をご紹介します。営業電話もなく、スムーズに比較検討できる安心の仕組みです。
「損をせずに手放したい」「信頼できる会社に任せたい」という方は、まずは無料査定からお試しください。
ReTrueの無料査定を試す