
投資用マンションの売却を考えている方にとって、「どの不動産会社に、どんな媒介契約で頼むべきか」は、売却成功の鍵を握る大切なポイントです。
媒介契約には、専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類があり、それぞれに報告義務や依頼の自由度、売却スピードなどに違いがあります。
「複数社に依頼すれば高く売れる?」「専任契約は縛られるだけ?」といった誤解も多く、選択次第では想定より安く売れてしまったり、余計なトラブルに繋がることも。
本記事では、媒介契約の仕組みと違いをわかりやすく解説し、自分に合った契約方法が判断できるようにまとめました。
媒介契約の選び方ひとつで、売却の満足度が大きく変わります。失敗しない売却のためにぜひ参考にしてください。
\オークション査定で高値売却を実現/
複数の不動産会社が同時に入札する「オークション形式」で、最も高い査定を提示した会社をご紹介します。営業電話もなく、スムーズに比較検討できる安心の仕組みです。
「損をせずに手放したい」「信頼できる会社に任せたい」という方は、まずは無料査定からお試しください。
ReTrueの無料査定を試す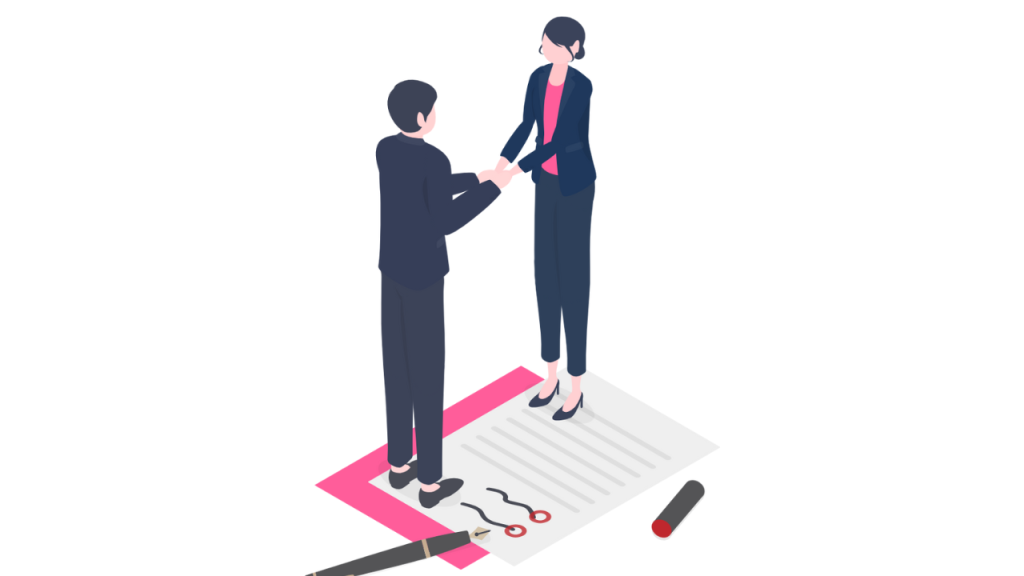
投資用マンションを売却するとき、まず必要になるのが「媒介契約」です。
これは、売主(オーナー)が不動産会社に対し「自分の物件を売ってほしい」と正式に依頼する契約であり、宅地建物取引業法で定められた重要なプロセスです。
この契約を結ぶことで、販売活動の範囲や報告の頻度、広告の扱いなどが明確になり、トラブルを防ぐことができます。
特に投資用マンションの場合、空室ではなく“入居中の状態(オーナーチェンジ)”で売却するケースも多いため、一般の自宅売却とは進め方が大きく異なります。
たとえば、入居者への通知や管理会社との連携など、複数の関係者が関わる点が特徴です。
「誰に何を任せるのか」「どこまで情報を公開するのか」を最初に整理しておくことで、スムーズな売却活動が可能になります。
媒介契約の目的は、売主と不動産会社の間に明確なルールを設けることにあります。
口頭だけの依頼では、広告掲載の範囲や報告義務、責任の所在が曖昧になり、のちに「聞いていなかった」「そんな約束ではなかった」といったトラブルに発展しかねません。
媒介契約を結ぶことで、不動産会社は売却活動を正式にスタートできます。
たとえば、レインズ(不動産流通機構)への登録や広告掲載、ポータルサイトへの出稿、買主への資料開示など、法的にも業務を行う根拠が整うのです。
つまり、「査定」まではあくまで提案段階であり、「媒介契約」を結ぶことで初めて“販売が動き出す”という流れになります。
オーナーにとっては、単なる形式的な書面ではなく、売却成功へのスタートラインと考えるのが正解です。
投資用マンションの売却では、居住用とは異なる実務上の配慮が必要です。
最大のポイントは「入居者がいる状態で販売を進める」ケースが多いこと。
家賃や契約期間、敷金の有無などの情報は、買主にとって“利回りを判断する重要な材料”になります。
ただし、賃貸借契約書や入居者情報の扱い方を誤ると、入居者との信頼関係を損ねるおそれもあります。
たとえば、レントロール(家賃表)を公開する際には個人情報を伏せ、管理会社経由で必要な部分だけを開示するなど、慎重な対応が求められます。
こうした細やかな情報管理が、スムーズな交渉と高値売却に繋がるポイントです。

投資用マンションを売却する際に結ぶ媒介契約には、主に3つの種類があります。
それぞれ「どこまで独占的に依頼するか」「どんな報告義務があるか」が異なり、売却スピードや管理のしやすさにも大きく関わります。
下の表は、3種類の契約を一目で比較したものです。
| 契約種別 | 他社への依頼 | レインズ登録義務 | 報告義務 | 売主が自分で買主見つけられるか |
|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 不可 | 5営業日以内 | 1週間ごと | 不可 |
| 専任媒介 | 不可 | 7営業日以内 | 2週間ごと | 可 |
| 一般媒介 | 可 | 義務なし | 義務なし | 可 |
この違いは、単なる形式の違いではなく「売却戦略そのもの」に直結します。
たとえば、短期で確実に売りたいのか、なるべく高く売りたいのか、あるいは複数社を比較したいのかなど、その目的によって、最適な契約は変わってきます。
3種類の中で、最も密に販売活動を行う契約です。
売主は他の不動産会社に依頼することができず、自分で買主を見つけて契約を進めることもできません。
その代わり、不動産会社は強い販売責任を負い、1週間に1回以上の販売報告を義務付けられます。
また、契約締結から5営業日以内に「レインズ」への登録が義務付けられています。
レインズ(REINS)とは、不動産流通機構が運営する“業者専用の物件データベース”のことです。
日本全国の不動産会社がこのシステムを通じて情報を共有しており、登録することで他社の営業担当や買主側の仲介会社も物件情報を閲覧できるようになります。
つまり、専属専任媒介を結ぶと、1社が中心になって販売活動を進めながら、同時に全国のネットワークを使って広く買主を探せる体制が整うというわけです。
「短期間で確実に売りたい」「信頼できる1社に全て任せたい」というオーナーに向いており、
実際にこの契約を選んだオーナーの中には、広告開始から2週間で成約した例もあります。
スピードと管理の一貫性を重視する場合に最も効果的な契約形式です。
専属専任と一般媒介の中間にあたる契約形式です。
他社に同時依頼することはできませんが、売主自身が自力で買主を見つけることは可能です。
販売活動の自由度と、不動産会社の責任範囲のバランスが取れているのが特徴です。
報告義務は2週間に1回、レインズ登録も7営業日以内と定められており、一定の透明性を保ちながらも、売主が主体的に動ける余地があります。
たとえば、「知人や既存の顧客ネットワークを通じて買主候補がいるが、販売活動はプロに任せたい」という場合には、この契約が最も適しています。
実務の現場でも、投資用マンションの売却で最も多く利用される形式がこの専任媒介契約です。
1社に集中して情報管理できるため、広告掲載の重複や価格の食い違いを防ぎ、安定した交渉がしやすくなります。
複数の不動産会社に同時に売却依頼できる契約形式です。
売主の自由度は最も高く、「どの会社が一番動いてくれるか」を試す“テスト販売”のような使い方もできます。
ただし、販売責任が分散し、各社の動きに温度差が出やすい点には注意が必要です。
レインズ登録義務や報告義務はなく、どの会社がどんな活動をしているかをオーナー自身が把握しづらくなります。
また、複数社が同じ物件を掲載するため、ポータルサイト上で情報が重複し、買主から見て“売れ残り物件”の印象を与えることもあります。
実際に、「3社に一般媒介で依頼した結果、掲載価格に差が出て市場評価が不安定になり、問い合わせが減った」という例も少なくありません。
一見“たくさんの会社に任せた方が早く売れそう”に思えますが、現実には誰も主体的に動かなくなるリスクがあるのです。
そのため、一般媒介は「まず市場の反応を見たい」「自分でも積極的に動ける」オーナーに向いています。
逆に、売却を急ぐ場合や、価格交渉を一元化したい場合は専任系を選んだ方が成果につながりやすいでしょう。
| 契約の特徴 | メリット | デメリット | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 担当が集中して動く/進捗が早い | 自分で買主を探せない/自由度が低い | 早期売却・担当を信頼して任せたい人 |
| 専任媒介 | 販売の一元管理と一定の自由度を両立 | 他社への依頼不可 | バランス重視・一般的な売却希望者 |
| 一般媒介 | 複数社に依頼できる自由度 | 責任分散・価格競争・売れ残り印象 | 比較検討・情報収集段階の人 |
このように、媒介契約は書面上の形式というよりも「売却をどう進めるかの方針表明」になります。
信頼できる不動産会社と適切な契約形式を選ぶことで、販売スピード・成約価格・トラブルリスクが大きく変わります。
次の章では、この3種類の契約が実際に売却スピードや価格にどのような差を生むのかを、事例を交えて詳しく解説していきます。

媒介契約の種類によって、販売の進み方や交渉の流れが少しずつ異なります。
同じ物件でも、依頼の仕方や情報の扱い方で成約までの期間や価格が変わることがあります。
ここでは、専任系(専任・専属専任)と一般媒介で、どのような違いが生まれやすいかを見ていきます。
専任媒介や専属専任媒介のように、1社に販売を任せる契約では、交渉や広告の窓口が一つになります。
担当者が一貫して動くことで、情報が整理されやすく、売主と買主のやり取りも落ち着いて進む傾向があります。
広告内容や掲載価格が統一されていれば、買主にとっても分かりやすく、信頼を持ってもらいやすい環境になります。
逆に、同じ物件で異なる条件が表示されていると「本当の情報はどれなのか」と不安に感じる人も少なくありません。
専任系では、こうした“情報の統一性”を保ちやすい点がメリットの一つといえます。
販売活動を担当する会社が一つに絞られている分、進捗の報告も早く、調整や修正もスムーズに行えます。
たとえば、専任媒介で販売を進めたワンルームでは、販売開始から約3週間で成約に至った事例があります。
週ごとの反響を共有しながら、タイミングを見て価格を微調整したことが功を奏した形です。
一般媒介は複数の会社に同時依頼できるため、依頼の自由度が高い契約です。
一方で、各社が独自に広告を出すことが多く、情報の扱い方に違いが出やすくなります。
たとえば、同じ物件でも「A社では2,180万円」「B社では2,150万円」と異なる価格で掲載されると、
買主が「値下がりしているのでは?」と受け取ってしまうことがあります。
こうした状況が続くと、市場全体での印象が下がり、交渉時に価格を下げざるを得なくなることもあります。
また、問い合わせ窓口が複数になることで、買主側から見ると「どの会社に話をすればいいのか分かりにくい」という声もあります。
結果として、興味を持った買主が離れてしまうことも考えられます。
一般媒介は、まだ売却を急いでいない段階や、まず相場の反応を知りたいときに使いやすい方法です。
ただし、情報管理を複数の会社に任せる分、広告内容のチェックや連絡の整理はオーナー自身も関与する必要があります。

媒介契約にはそれぞれ特徴がありますが、「どれが正解」というよりも、オーナーが何を重視するかによって向き・不向きが変わります。
ここでは、目的別に考えやすいようタイプ別に整理しました。
自分の状況に近い項目を意識して読むと、どの契約が合うかが見えてきます。
「できるだけ早く現金化したい」「買主との交渉を最短でまとめたい」といったケースでは、専属専任媒介が向いています。
この契約では、1社の担当者がすべての販売活動を統一して進めるため、対応の重複や情報の混乱が少なく、反応の早さを保ちやすいのが特徴です。
レインズへの登録も義務化されており、他の業者経由で買主が見つかる可能性も広がります。
たとえば、築浅・駅近といった人気条件の物件で「すぐにでも買いたい人が見つかりそう」というケースでは、
スピード感のある販売体制を整えやすい契約といえるでしょう。
「特定の担当者を信頼している」「販売戦略を一緒に考えてほしい」というオーナーには、専任媒介が合いやすいです。
専属専任と違い、売主が自分で買主を見つけることもできます。
そのため、販売を1社に任せつつも、オーナー自身も紹介やネットワークで動ける柔軟さがあります。
たとえば、過去に購入を担当してくれた営業担当の姿勢を信頼している場合や、
管理も同じ会社に任せている場合は、この契約を選ぶとやり取りがスムーズです。
情報共有が早く、広告・内見・交渉の方向性も統一しやすいため、安心感を持って販売を進められます。
「まずは市場の反応を知りたい」「複数の会社の提案を比較したい」という段階では、一般媒介が検討しやすい契約です。
同時に複数の会社へ依頼できるため、それぞれの対応力や販売方針を見比べることができます。
一方で、情報が分散しやすく、広告内容に統一感を持たせにくい点には注意が必要です。
販売期間が長くなるほど、掲載価格のばらつきが出やすくなるため、
「動きの良い会社を見極める」「反響があった1社に専任で切り替える」など、
一定期間で見直す前提で使うと効果的です。
どの契約が合うか迷ったら、次の3つの視点で考えると整理しやすくなります。
1|物件の販売難易度(築年・立地)
築浅・駅近など反響が得やすい物件は、専任でも一般でも売れやすい傾向。
反対に築古や郊外立地では、担当者が粘り強く動く専任系が安心。
2|自分の売却目的(スピード/価格)
「早く売りたい」なら専属専任、「少しでも高く売りたい」なら提案を比較できる一般媒介も選択肢。
3|信頼できる担当者がいるかどうか
担当者の対応力や報告の丁寧さは、契約形態よりも結果を左右する要素。
もし“この人なら任せられる”と感じる相手がいるなら、専任で動いた方が効率的な場合もあります。
媒介契約は、書類の形式ではなく「どんなスタンスで売却を進めるか」を決める選択です。
焦らず、自分の目的や担当者との相性を考えながら選ぶことが、納得のいく結果につながります。

媒介契約は、売主と不動産会社との正式な契約行為です。
そのため、契約内容に反した行動をとると、状況によっては「違約金」や「実費請求」が発生する場合があります。
ここでは、よくある注意点と、違約金が発生しやすいパターンを整理しておきます。
専任媒介や専属専任媒介では、他の不動産会社に重ねて依頼することや、自分で買主を見つけて契約を進めることが制限されています。
この契約期間中に、他社経由または自己取引で売却してしまうと、違約金を請求されるケースがあります。
たとえば、専属専任で依頼していた物件を、他社の紹介で成約させてしまった場合などがこれにあたります。
「自分で買主を見つけたから問題ないだろう」と判断するのは危険です。
契約書の「禁止事項」や「違約条項」をよく確認しておきましょう。
媒介契約は通常3か月を上限として結ばれます。
やむを得ない事情があれば途中で解約することも可能ですが、販売活動がすでに始まっている場合には、実費分の費用を請求されることがある点に注意が必要です。
特に、売主の都合によるキャンセルや、契約期間中に他社へ切り替える場合などは、
不動産会社が負担した広告費・資料作成費などを精算として求められることがあります。
こうしたトラブルを防ぐには、契約を結ぶ前に「途中解約時の扱い」や「費用負担の範囲」を担当者に確認しておくことが大切です。

投資用マンションを売却する際には、売却価格だけでなく「どんな費用がかかるか」も把握しておくことが大切です。
どの費用も金額は物件の条件によって多少変動しますが、全体の流れを理解しておくことで、手取り金額の見通しを立てやすくなります。
ここでは、投資用不動産売却時にかかる、主な費用についてご紹介します。
仲介手数料は、不動産会社へ支払う成功報酬です。
物件が成約したときにのみ支払うもので、売れなければ発生しません。
媒介契約の種類(専任・一般など)によって金額が変わることはありません。
たとえば、2,000万円でマンションが売れた場合、手数料の上限は
2,000万円 × 3% + 6万円 = 66万円(+消費税) となります。
売買契約書を作成するときには、印紙税がかかります。
これは契約書に「印紙」を貼付することで納める税金で、金額は契約金額によって変わります。
たとえば、1,000万円超〜5,000万円以下の契約書であれば、印紙税は1万円。
5,000万円超〜1億円以下なら3万円が目安です。
また、売却時に住宅ローンなどの残債がある場合、抵当権を抹消する登記手続きが必要です。
司法書士に依頼することが一般的で、費用の目安は3万円前後。
銀行によっては別途「抹消手数料」がかかる場合もあります。
登記簿謄本や印鑑証明書など、契約・登記に必要な書類を取得するための費用です。
1通あたり数百円〜1,000円前後と小額ですが、複数枚必要になるケースもありま
法人名義の物件では、会社の登記簿や印鑑証明などが追加で必要になる場合があるため、やや多めに見ておくと安心です。
区分マンションを売却する際には、管理会社へ「重要事項調査報告書」を依頼します。
これは、管理費や修繕積立金の状況、滞納の有無、管理組合の運営状況などをまとめた書類で、
買主側が安心して購入判断をするために欠かせない資料です。
発行手数料は管理会社によって異なりますが、一般的に1件あたり2万円前後が目安です。
発行まで数日かかることもあるため、売却活動を始める前に依頼しておくとスムーズです。
引き渡し時の状態に応じて、鍵交換や室内クリーニングなどの費用が発生する場合があります。
オーナー自身が居住していた物件や、入居者が退去した直後の物件では、
次の所有者に気持ちよく引き渡せるよう最低限のメンテナンスを行うことが多いです。
費用の目安は、鍵交換で5,000〜1万円、簡易清掃やクリーニングで2〜3万円程度。
「現状有姿(ありのまま)」での引き渡しが契約条件になっている場合は不要ですが、
販売印象を整える意味では、不動産会社に相談して判断するのがおすすめです。

投資用マンションを売却して利益(売却益)が出た場合、その利益に対して税金がかかります。
「譲渡所得税」や「住民税」といった税金は、売却益の金額や所有期間によって税率が変わります。
売却を検討する際には、税金の知識も重要になりますので事前に確認しておきましょう。
マンションを売却して得た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、所得税と住民税の対象になります。
課税されるのは、単純な売却価格ではなく、「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で算出される利益部分です。
たとえば、
この場合、譲渡所得は「2,200万円 −(1,800万円+100万円)=300万円」となります。
また、所有期間によって税率が異なります。
| 譲渡所得の種類 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 5% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |
※所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定されます。
短期譲渡に該当する場合は税率が高くなるため、
売却時期を1年ずらすだけで税額が半分近く変わるケースもあります。
このため、売却のタイミングを決める前に、所有期間を確認しておくことが大切です。
平成25年から令和19年までは、「復興特別所得税」が上乗せされます。
これは、東日本大震災の復興財源として2013年から導入されているもので、
所得税額の2.1%(=税率換算で約0.315%)が追加で課税されます。
たとえば、長期譲渡で所得税15%の場合、
実際には「15% × 1.021=15.315%」が適用されます。
少額ではありますが、計算上は最終的な税額に関わるため、申告時には含めて計算します。
出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」
不動産を売却して利益が出た場合、翌年の2月16日〜3月15日頃に確定申告を行います。
申告をしないと税金が確定しないため、忘れずに対応する必要があります。
申告時に必要となる主な書類は以下の通りです。
・売買契約書(売却時・購入時の両方)
・仲介手数料や司法書士報酬などの領収書
・登記事項証明書
・譲渡費用の明細(印紙代・測量費など)
・取得時の登記費用・リフォーム費用の記録(ある場合)
譲渡損失(赤字)になった場合でも、確定申告を行うことで、
他の所得との損益通算や翌年以降への繰越控除が使えるケースがあります。
税務上の扱いは個人によって異なるため、不明点は税理士や不動産会社に確認しておくと安心です。
投資用マンションの売却を成功させるには、「どの媒介契約を、どんな会社と結ぶか」が重要なポイントになります。
契約の種類によって販売活動の進め方やスピード、報告の頻度、情報管理の仕方が異なるため、オーナーの目的に合わせた選択が欠かせません。
たとえば、早く売りたい場合は専属専任媒介、信頼できる担当者に任せたいなら専任媒介、複数社を比較しながら様子を見たいなら一般媒介が向いています。
どの形式を選ぶにしても、担当者とのコミュニケーションの密度と情報の透明性が結果を左右することは共通しています。
また、媒介契約を結ぶ前には、広告費の負担や解約時の取り扱いなど、費用面の条件も必ず確認しておきましょう。
後から「そんな費用がかかるとは知らなかった」というトラブルを防ぐためには、書面と説明の両方で内容を理解しておくことが大切です。
不動産売却は大きな取引になりますので、焦らず、自分の目的や状況に合った媒介契約を選ぶことで、納得のいく売却につながります。
信頼できる不動産会社と相談しながら、安心して次のステップへ進んでいきましょう。
\オークション査定で高値売却を実現/
複数の不動産会社が同時に入札する「オークション形式」で、最も高い査定を提示した会社をご紹介します。営業電話もなく、スムーズに比較検討できる安心の仕組みです。
「損をせずに手放したい」「信頼できる会社に任せたい」という方は、まずは無料査定からお試しください。
ReTrueの無料査定を試す