
マンションを所有していると「この建物は地震にどれくらい強いのだろう?」と気になる瞬間があります。
特に地震が多い日本では、建物の耐震性は“安心して住めるかどうか”だけでなく、“どれくらいの価格で売れるか”にも大きく影響します。同じ築年数でも耐震基準や構造の違いによって価値が変わることも珍しくありません。
この記事では、旧耐震と新耐震の違い、耐震等級、Is値などの耐震指標、さらには制震・免震といった構造の特徴まで、マンションの耐震性を見極めるためのポイントをわかりやすく解説します。
売却を検討している方や、これから投資用マンションの価値を見直したい方にとって、必ず役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
\オークション査定で高値売却を実現/
複数の不動産会社が同時に入札する「オークション形式」で、最も高い査定を提示した会社をご紹介します。営業電話もなく、スムーズに比較検討できる安心の仕組みです。
「損をせずに手放したい」「信頼できる会社に任せたい」という方は、まずは無料査定からお試しください。
ReTrueの無料査定を試す投資用の分譲マンションであっても、区分所有者が単独で建物全体の耐震診断を行うことは、通常ありません。耐震診断はマンションの管理組合が主体となって実施するのが一般的です。
さらに、マンション全体の耐震診断には100万円単位の費用がかかることも多く、修繕積立金や一時金を用いて住民全体で負担するのが一般的です。
旧耐震のマンションでは診断結果によって補強工事が必要になる場合もあり、費用負担や見た目の変化をめぐって住民間の合意形成が欠かせません。
では、オーナーは耐震性をどのように確認すればよいのでしょうか?
まずは管理組合から情報を得ることが最初のステップです。議事録や長期修繕計画、設計図書、過去の診断履歴などを確認すれば、建物の耐震性に関する一定の情報が把握できます。
また、1981年6月1日以降に建築確認を受けた新耐震基準の建物であれば、基本的な安全性は確保されています。自治体によっては特定建築物の耐震診断を義務付けている場合もあるため、該当するかどうかを調べることも有効です。
結論として、投資用マンションの耐震診断をオーナーが「自分で手配する必要は基本的にありません」。しかし、売却や長期保有を考えるうえで、耐震基準と建物の状態を理解しておくことは大きな武器になります。
まずは管理組合の情報を確認し、建物の耐震性に関する知識をしっかり身につけておくことで、資産価値を適切に判断できるようになります。

マンションの耐震性能を判断する際、「旧耐震」と「新耐震」は非常に重要な区分です。とくに投資用マンションでは、耐震基準の違いが融資条件・買い手の幅・売却価値に直結するため、築年数以上の判断材料として注目されています。同じエリア・同じ築年数であっても、基準が異なるだけで収益性や出口戦略に大きな差が出ることがあります。
旧耐震基準は、1981年5月31日以前に建築確認を受けた建物に適用されていた基準です。背景には、1978年の宮城県沖地震による甚大な被害があり、この地震をきっかけに建築物の耐震性を見直す必要性が強く認識されました。
旧耐震基準で求められていたのは「震度5程度の揺れで倒壊しない」レベルです。現在の地震観測や想定と比較すると安全性には大きな隔たりがあり、この年代の物件は構造によって耐震性に不安が残るケースも見られます。
投資用マンションとして検討する際は、特に以下の点が影響します。
旧耐震物件は融資が厳しくなる傾向があり、買主の選択肢が限定されることから、売却までに時間がかかる可能性があります。また、建物ごとの個体差が大きいため、耐震診断の実施状況や補強工事の有無を確認することが不可欠です。
一方で、都心など賃貸需要が極めて強いエリアでは、旧耐震であっても稼働率を確保できるケースがあります。しかし出口戦略の難易度は高いため、購入価格とのバランスが投資成否を左右します。
1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物は、いわゆる「新耐震基準」で建てられています。宮城県沖地震の教訓を踏まえ、建物は震度6強〜7クラスの大地震でも倒壊しないことが求められるようになりました。
新耐震基準では、建物の粘りや変形性能を重視する設計思想が導入され、旧耐震に比べて大幅に安全性が向上しています。
投資用マンションの市場でも、この基準以降の物件は融資評価が安定し、売却時も買い手がつきやすい傾向があります。
ただし、新耐震といっても建てられた年代や構造の工夫によって性能にばらつきがあるため、図面構造・修繕履歴・管理状態を確認する姿勢は必要です。
2000年には、建築基準法がさらに改正され、主に木造住宅の耐震性向上を目的とした新たな規定が加わりました。
壁量(耐力壁の量)・接合部の強化・基礎仕様などのチェックが厳密化され、より実態に沿った耐震設計が求められるようになりました。
鉄筋コンクリート造(RC造)のマンションへの直接的な影響は限定的ですが、それでも2000年基準以降の物件は、設計方針や建築管理の精度が全体的に向上しているため、市場評価は比較的堅調です。
投資用マンションにおいては、この年代の物件は設備仕様も比較的新しく、賃貸需要・流動性ともにバランスの良いゾーンとされることが多く、購入検討のしやすい年代といえます。

耐震等級は、建物がどの程度の地震に耐えられるかを示す“耐震性能の指標”です。住宅の品質確保を目的とした「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」によって定められており、等級1〜3の3段階に分かれています。
マンション購入の場面ではあまり強調されない項目ですが、投資用マンションの長期保有・出口戦略を考えるうえで、物件の安全性と市場評価を左右する要素のひとつといえます。
一般の方にとっては少し馴染みにくい指標ですが、耐震等級を理解しておくことで、建物の設計思想や将来の修繕の方向性を読み取りやすくなります。
耐震等級1は、現行の建築基準法を満たす最低ラインの耐震性能です。
想定されるのは「数百年に一度発生するレベルの地震(震度6強〜7)」に対して倒壊・崩壊しないこと。日本国内の一般的なマンションや住宅は、この等級1を満たす設計で建てられています。
投資用マンションの場合、ほとんどの物件がこの等級に該当します。等級1でも十分な耐震性がありますが、物件によっては構造バランスや建物形状の違いから揺れやすさに差が出るため、図面や構造計算に関する資料を確認しておくと安心です。
耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の強さを持つ建物です。
「学校」「避難所」などの防災拠点にも使われる性能で、住宅としては上位グレードに位置づけられます。
投資用マンションでは、等級2の物件はまだ多くありませんが、もし存在すれば市場において差別化できるポイントになります。
賃貸募集時に「高い耐震性能」を訴求できたり、購入希望者へ建物の強度を明確に説明できるため、長期的な資産価値の安定に寄与します。
また、耐震等級2を取得している新築マンションは、分譲時にブランド価値が付く傾向があり、将来の売却時にも一定のプラス要素となることがあります。
耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の強さを持つ最上位の耐震性能です。
消防署・警察署といった災害時の拠点施設に求められるレベルで、建物が大規模地震の際にも機能を保つことを想定しています。
区分マンションで等級3を取得しているケースは非常に少ないものの、もし投資対象として出会えれば、耐震性と資産性の両方で高く評価できる物件になります。
地震リスクに敏感な入居者が増えていることから、賃貸市場でも選ばれやすく、売却時にも大きなアピールポイントになります。
耐震等級は、「住宅性能評価書」で確認できます。新築マンションの場合は、所有者が評価書を取得していることもありますが、すべての建物が評価を受けているわけではありません。
投資用マンションの購入時には、下記のように確認すると精度が上がります。
・「住宅性能評価書」の有無
・「構造計算書」「設計図書」での耐力壁の配置や構造仕様
・管理組合が保有している資料(長期修繕計画・過去の診断結果)
評価書がなくても、建物の情報を複合的に見ることで耐震性能の方向性を掴むことはできます。
特に長期保有を前提とする投資では、建物の安全性が最終的に収益性の安定にもつながるため、耐震等級について理解しておくと良いでしょう。

耐震診断は、建物が現在どの程度の地震に耐えられる状態なのかを客観的に評価するための調査です。
特に、1981年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建物や、築年数が長く劣化が進んでいる建物、増改築を行う前、あるいは大きな地震の後に不安を感じた場合などは、診断を受けるタイミングとして適しています。
また、行政の補助金制度を活用したいときや、建物の売却を検討する際にも、耐震診断は建物の価値を明確にする重要なプロセスになります。
マンションや住宅の耐震性能は、建物の強さ(強度)と揺れに耐える粘り(靭性)に加え、建物形状や老朽化の状態を総合的に判断して評価されます。その際、建物の構造に応じて次の2つの指標が用いられます。
Is値(耐震指標 Is:構造耐震指標)は、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造(S造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)など、マンションを含む非木造建物の耐震診断で使われる指標です。
Is値は「建物の強さ × 建物の粘り × 建物の配置(形状) × 劣化度」を総合的に評価して算出されます。
診断の際には、構造壁・柱・梁の状況、劣化の程度、建物の重さ、偏心(建物が左右非対称な構造になっている状態)など、多くの要素が反映されます。
Is値では、一般的に以下のような基準が目安とされています。
・0.6以上:大地震でも倒壊する危険性が低い
・0.3~0.6:補強を検討すべき状態
・0.3未満:大地震で倒壊の危険性が高い
投資用マンションでは、Is値が明確であることは大きなメリットになります。
金融機関の融資評価が安定しやすく、購入希望者も安心材料として判断できます。
逆にIs値が低い場合は、売却時に説明責任が必要になったり、買い手のターゲットが限定されるため、収益性への影響も考えられます。
Iw値は、木造住宅の耐震診断に用いられる指標です。
木造は非木造と構造の仕組みが大きく異なるため、耐力壁の数や配置、接合部の状態、基礎の仕様などが診断の中心になります。
Iw値は、建物の「耐力壁の量(壁量)」「壁の配置バランス」「老朽化の状況」などを総合的に評価し、補強すべき箇所を明確にするための指標でもあります。
木造住宅は劣化の進み方に個体差が出やすく、シロアリ被害や湿気による腐朽などが耐震性に大きく影響するため、Iw値の診断は非常に重要です。
具体的には、Iw値が低いほど建物の耐震性に問題があることを示し、壁量が不足している、接合部が弱くなっているなど、具体的な構造上の課題を読み取ることができます。
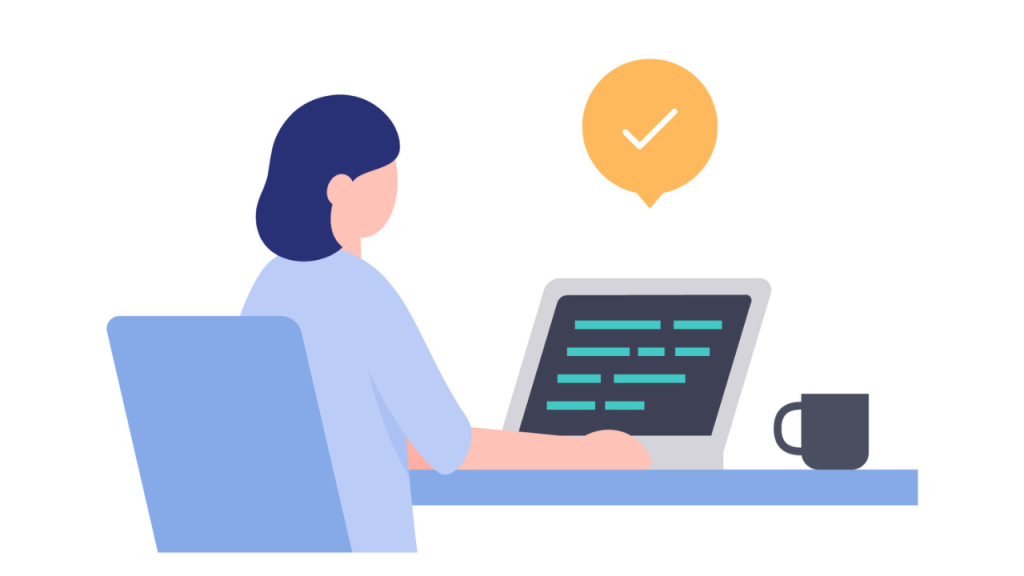
耐震診断にはいくつかの方法があり、建物の構造(非木造/木造)や診断の目的、求める精度によって選択肢が変わります。
投資用マンションの場合、建物全体の安全性を把握するために非木造向けの診断方法が中心になりますが、戸建て投資やアパート投資では木造向けの診断方法が使われます。ここでは、それぞれの診断方法をわかりやすく整理します。
マンションなどの非木造建物では、建物の規模や求められる精度に応じて「一次診断」「二次診断」「三次診断」という3段階の方法が用いられます。
一次診断は、図面や基本情報をもとに行う比較的簡易な診断です。
壁量や柱・梁の配置を確認し、建物のおおまかな耐震性を判断します。
現地調査が限定的なため費用は抑えられますが、精度は高くありません。
初期判断として「建物に耐震上の問題がありそうか」を把握する段階に適しています。
二次診断は、非木造の耐震診断で最も一般的かつ実務的に使われる方法です。
図面だけでなく現地調査も行い、コンクリート強度や鉄筋の配筋、劣化の状況、構造バランスなどを総合的に評価します。
Is値(耐震指標)もこの段階で精度高く算出され、建物の具体的な耐震性を把握できます。
投資用マンションの場合も、多くの管理組合が二次診断を採用しており、売却時の資料として提示されることがあります。
三次診断は、構造専門家による高度な解析を行う最も精密な診断方法です。
建物の立体挙動や部材ごとの応力を数値的に解析し、震度6強〜7クラスの地震エネルギーに対する挙動まで詳細に検討します。
費用と時間はかかりますが、耐震補強工事の計画や建物の再生プロジェクトなど、精密な判断が必要なケースでは非常に有効です。
大規模マンションや公共建築物で採用されることが多い診断方法です。
木造住宅は非木造とは構造の仕組みが大きく異なるため、診断の方法も別体系になります。
自治体が提供するチェックシートを使い、住まい手自身が目視で行う簡易診断です。
基礎の状態やひび割れ、外壁の劣化状況を確認し、耐震性の大まかな傾向を把握します。
建物の図面確認や現地調査をもとに、壁量や配置バランス、老朽度などを評価する方法です。
多くの木造住宅で採用される一般的な診断で、Iw値(木造耐震指標)もこの段階で算出されます。
より詳細に構造部材や基礎の状態を調査し、構造計算に基づいて耐震性能を算定する方法です。
補強計画の策定や建て替えの検討など、精度の高い判断が必要な場合に適用されます。

マンションの安全性を考えるとき、構造の種類はとても重要なポイントになります。
建物がどのように地震エネルギーを受け止め、吸収し、逃がすのかは、揺れの大きさや被害の出やすさに直結するためです。
特に投資用マンションでは、構造の違いが「入居者の安心感」「賃貸需要」「長期的な資産価値」に影響することも少なくありません。ここでは、代表的な3つの構造をわかりやすく整理します。
耐震構造は、もっとも一般的に採用されている地震対策の工法です。建物そのものを強くし、揺れに耐えられるよう柱・梁・壁などの強度を高める設計が行われています。
耐震構造のメリットは、構造がシンプルでコストを抑えやすく、多くのマンションで採用されているため安心材料として認知度が高い点です。また、構造が複雑ではないため、修繕計画を立てやすく、長期的な維持管理もしやすくなります。
一方で、揺れそのものは建物に伝わりやすく、大地震の際には家具の転倒や内部被害につながることがあります。とはいえ、多くの区分マンションが耐震構造で安全に建てられているため、一般的な投資用物件ではこの構造がスタンダードと言えます。
制震構造は、建物内部に「制震ダンパー」と呼ばれる装置を組み込み、揺れのエネルギーを吸収して建物への負担を減らす仕組みです。揺れを“逃がす”のではなく、“吸収して和らげる”タイプの地震対策です。
メリットとしては、揺れの大きさを抑えやすく、繰り返しの中小地震に対してもダメージが少ない点が挙げられます。居住者にとっては、地震の際に体感する揺れが軽減されるため安心感が高く、近年は新築マンションで採用例が増えています。
デメリットは、耐震構造と比較すると建築コストが上がりやすい点です。また、制震ダンパー自体の点検や交換が必要になるケースもあり、長期の維持管理に一定の専門性が求められます。
投資用マンションとしては、制震構造の物件は“地震に強い付加価値”を打ち出しやすく、入居者へのアピールポイントになります。
免震構造は、建物を地面から絶縁するように「免震ゴム」や「積層ゴム」を基礎部分に設置し、地震の揺れを建物に伝えにくくする工法です。揺れそのものを建物に伝えないため、3つの構造の中でもっとも体感揺れを抑えられるのが特徴です。
免震構造の最大のメリットは、震度6強〜7クラスの大地震でも建物内の揺れを大幅に低減できる点です。家具の転倒リスクが小さく、地震後の建物の損傷も最小限に抑えられることが多いため、安心性ではトップクラスと言えます。
その反面、建築コストが高く、物件価格にも反映されやすいというデメリットがあります。また、免震装置の維持管理には専門的な点検が必要で、修繕費が一般的な建物より高くなることもあります。
投資用マンションでは、免震構造は高級志向の物件で採用されることが多く、入居者層や物件のブランド力にも影響します。“安心性を重視する層”に刺さりやすく、売却時の資産価値も安定しやすい構造です。

地震への備えを考えるとき、建物の構造や築年数だけでは万全とは言えません。
物件が建っている場所のリスクや、予期せぬ被害に対応できる保険の仕組みまで含めて考えることで、より安全性の高い不動産選びが可能になります。
特に投資用マンションでは、災害リスクの理解が「入居者の安心感」「空室リスク」「資産価値の維持」に直結するため、必ずチェックしたい項目です。
ハザードマップは、災害時にどのような危険が起こり得るかを地図上で確認できるツールです。
地震の揺れやすさだけでなく、液状化、浸水、土砂災害など、地域によって異なるリスクが視覚的に理解できます。
同じ駅の徒歩5分圏内でも、エリアや地盤の違いによって揺れ方や液状化のリスクが大きく変わることがあります。たとえば、埋立地や河川沿いでは液状化の可能性が高く、谷地形では地盤が揺れやすい傾向があります。
投資用マンションでは、こうした立地の特徴が賃貸需要や将来的な資産性にも影響してくるため、物件調査の初期段階で必ず確認しておきたいポイントです。
また、自治体が提供するハザードマップは無料で利用でき、詳細な地盤情報を確認できる地域も増えています。気になる物件がある場合は、区単位だけでなく丁目レベルまで細かくチェックすると精度が高まります。
建物構造や立地をどれだけ慎重に選んだとしても、自然災害を完全に避けることはできません。
そこで重要になるのが、火災保険とセットで加入する地震保険です。
地震保険は、地震そのものだけでなく、噴火や津波による損害にも対応しています。万が一のときに再建・修復の資金を確保できるため、物件オーナーにとってはリスクヘッジの大きな柱となります。
投資用マンションの場合、地震保険はキャッシュフローの安定性にも関わります。
大きな地震で建物が損傷した場合、保険金が下りることで修繕費をカバーでき、持ち出しを最小限に抑えることができます。
なお、地震保険には「全損」「大半損」「小半損」「一部損」という認定区分があり、損害の割合に応じて受け取る保険金額が変わります。内容を正しく理解し、適切な補償額を設定すると、万が一の時に大きな助けとなります。
地震に強いマンションを見極めるには、耐震基準・耐震等級・Is値・構造・立地リスクを総合的に判断することが欠かせません。
これらは専門的に聞こえますが、投資用マンションの資産価値や将来の売れやすさにも直結する重要なポイントです。
建物の耐震性が高いほど、入居者に選ばれやすく、長期保有でも管理が安定し、売却時にも評価されやすくなります。
逆に、旧耐震の物件や診断が行われていない物件は、出口戦略で差が出ることがあるため、早めに現状を把握しておくことが大切です。
もし「自分の物件はどれくらいの耐震性なのか」「売却するとしたら今の価値はどれくらいなのか」と気になる場合は、一度プロに査定を依頼してみるのが有効です。
耐震性も含めた建物の状態を踏まえ、無理のない売却時期や価格の目安が把握できます。
投資用マンションの売却は、情報が整っているほどスムーズに進みます。
不安がある場合や、まずは参考として知りたい場合でもお気軽にご相談ください。
\オークション査定で高値売却を実現/
複数の不動産会社が同時に入札する「オークション形式」で、最も高い査定を提示した会社をご紹介します。営業電話もなく、スムーズに比較検討できる安心の仕組みです。
「損をせずに手放したい」「信頼できる会社に任せたい」という方は、まずは無料査定からお試しください。
ReTrueの無料査定を試す