
マンションのS造、RC造、SRC造、木造の違いとは?特徴やメリット・デメリットを解説
投資用マンションを購入する際、物件概要欄に必ず記載されている「構造」という項目。
そこには S造(鉄骨造)・RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)・木造 といった表記が並びます。
これらは単なる専門用語ではなく、物件の価値や将来の収益性を左右する重要な要素です。
構造によって、耐久性、防音性、建築コスト、修繕費、そして賃貸需要までもが変わります。
例えば、RC造やSRC造は防音性が高く入居者満足度が高い傾向がありますが、建築コストが高くなるため家賃設定や利回りにも影響します。
一方、S造や木造は建築費を抑えやすく高利回りを狙える反面、防音性や耐久性では劣る場合があります。
本記事では、各構造の特徴・メリット・デメリット、防音性比較、そして賃貸市場での人気傾向まで詳しく解説します。
これから投資用マンションを購入しようとしている方や、すでにオーナーとして運営している方にとって、長期的な資産運用の参考になる情報をまとめました。
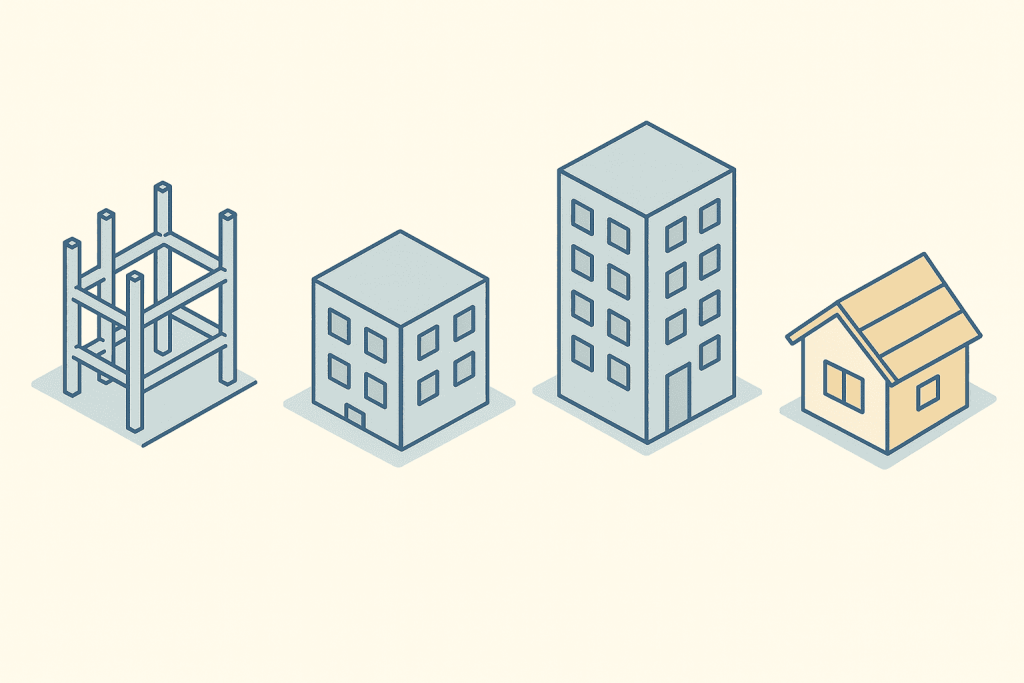
建物の構造とは、建物を支える柱・梁・壁などの「骨組み」の種類を指します。
使う素材や工法によって、大きく以下の4種類に分類されます。
構造の違いは、建物の耐震性・耐久性・遮音性・建築コストに影響します。
S造は「Steel(スチール)造」の略で、柱や梁に鉄骨を使用した構造です。
使用する鋼材の厚さによって軽量鉄骨造と重量鉄骨造に分かれます。
軽量鉄骨造は厚さ6mm未満の鋼材を使い、2〜3階建てのアパートや小規模マンションに多く採用されます。重量鉄骨造は厚さ6mm以上の鋼材を使い、5階以上の中高層マンションや商業施設でも使われます。
鉄骨は引っ張りや曲げに強く、耐震性にも優れています。また、部材が比較的軽量なため、施工がしやすく工期を短縮できるという特徴があります。ただし、鉄は錆びやすいため、防錆処理や定期的なメンテナンスが必要です。
RC造は「Reinforced Concrete(鉄筋コンクリート)」造の略です。
鉄筋で骨組みを作り、その周囲をコンクリートで固めた構造で、鉄筋の引っ張り強度とコンクリートの圧縮強度を組み合わせ、高い耐久性を実現しています。
この構造は耐震性・耐火性・防音性に優れており、都市部の分譲マンションや集合住宅で最も多く採用されています。外部や上下階からの騒音を遮る性能が高く、安定した室内環境を保ちやすいことが特徴です。
また、コンクリートは湿気や温度の変化にも強いため、建物の長寿命化にも寄与します。ただし、重量があるため地盤条件によっては基礎工事が大規模になる場合があります。
SRC造は「Steel Reinforced Concrete(鉄骨鉄筋コンクリート)」造の略です。
鉄骨の骨組みの周囲に鉄筋を組み、その全体をコンクリートで覆った構造で、鉄骨の柔軟性と鉄筋コンクリートの強度を兼ね備えています。
この構造は耐震性・耐火性・防音性のいずれも非常に高く、超高層マンションや大規模建築物に採用されることが多いです。特に地震時には鉄骨が揺れを吸収し、鉄筋コンクリートが建物の変形を防ぐため、非常に高い安全性を確保できます。
重量が大きく構造が複雑なため、建築には高度な技術と長い工期が必要です。その分、完成した建物は頑丈で耐用年数も長くなります。
木造は、柱や梁といった主要構造部に木材を使用する構造です。
日本の住宅では古くから主流で、戸建住宅や2〜3階建てのアパートに広く採用されています。
木材は軽量で加工しやすく、建築コストも比較的低く抑えられるのが特徴です。また、断熱性や通気性に優れており、室内環境を快適に保ちやすいという利点もあります。木の温もりや質感を好む人も多く、デザインの自由度も高いです。
一方で、耐火性や防音性は他の構造に比べて劣ります。また、湿気やシロアリ被害による劣化のリスクがあるため、定期的なメンテナンスや防虫・防腐処理が欠かせません。

建物の構造は、耐震性や耐火性、防音性、そして維持管理のしやすさなどに大きく影響します。
それぞれの構造には長所と短所があり、性能や特徴は一様ではありません。
ここでは、S造・RC造・SRC造・木造の代表的なメリットとデメリットを整理し、特徴をわかりやすく比較します。
S造は柱や梁に鉄骨を使う構造で、軽量鉄骨造(厚さ6mm未満の鋼材を使用)と重量鉄骨造(厚さ6mm以上の鋼材を使用)の2種類があります。
軽量鉄骨は2〜3階建てのアパートなどに多く、重量鉄骨は中高層マンションや商業施設にも採用されます。
1. 工期が短く、建築コストを抑えやすい
鉄骨部材はあらかじめ工場で製作され、現場ではボルトや溶接で組み立てる「プレファブ方式」が一般的です。
この方法はコンクリートの養生期間を必要としないため、天候の影響を受けにくく短期間で施工可能。
また、現場作業が少ない分、労務費や仮設費を抑えることができます。
2. 柔軟性があり、地震時の揺れを吸収しやすい
鉄骨は粘り強く、一定の変形に耐えられる「靭性」が高い材料です。
地震の揺れによって構造にかかるエネルギーを変形で吸収し、倒壊リスクを低減します。
適切なブレース(筋交い)配置や接合部設計により、揺れの分散効果を高めることができます。
3. 設計自由度が高い
鉄骨は強度あたりの重量が小さいため、梁や柱の断面をスリムにでき、広いスパンを飛ばす設計も可能です。
そのため、大空間や柱の少ない間取りなど、空間デザインの自由度が高いのも特徴です。
一方で、S造には構造的・物理的な弱点もあります。
これらは適切な設計や仕様選定でカバーできますが、知っておくことが重要です。
1. 防音性・断熱性がRC造やSRC造より低い
遮音性は「質量則」に従い、構造体が重いほど音を遮りやすい特性があります。
S造はRC造に比べ自重が軽く、壁や床が薄くなりがちなため、外部騒音や上下階の足音が伝わりやすくなります。
また、鉄は熱を伝えやすいため、断熱性能が低下しやすいのも特徴です。
これらを改善するには、二重床や二重壁、断熱材の充填などの仕様が必要です。
2. 錆び対策が必要
鉄骨は湿気や雨水にさらされると腐食します。
特に海沿いの地域や結露が発生しやすい場所では、錆びが進行しやすく、強度低下の原因になります。
そのため、防錆塗装や亜鉛メッキ処理、定期的な点検・塗り替えが欠かせません。
3. 耐火性能の確保が必須
鉄は高温に弱く、約500℃を超えると強度が急激に低下します。
火災時の安全性を確保するため、ロックウール吹付けや耐火被覆板などで鉄骨を覆う必要があります。
この耐火被覆が劣化・剥離すると、所定の耐火性能が保てなくなるため、点検・補修が重要です。
RC造は「Reinforced Concrete(鉄筋コンクリート)」の略で、鉄筋の引張強度とコンクリートの圧縮強度を組み合わせた構造です。
鉄筋は引っ張り力に強く、コンクリートは押しつぶす力に強いため、両者を一体化させることで高い構造性能を発揮します。
1. 防音性・断熱性が高く、快適な室内環境を維持しやすい
RC造は構造体自体の質量が大きく、音を遮る性能(遮音性)に優れています。
上下階や隣室からの生活音や外部騒音を軽減しやすく、特に床衝撃音や空気音に対して有効です。
また、コンクリートの厚みにより熱の伝わり方が遅く、夏は外の暑さが室内に届きにくく、冬は室内の暖かさを保ちやすい特徴があります。
2. 耐久性・耐火性に優れる
コンクリートは不燃材料であり、火災が発生しても構造部材が燃えることはありません。
さらに、鉄筋はコンクリートに覆われているため、外気や湿気から守られ、適切な維持管理をすれば数十年にわたって強度を保ちやすい構造です。
耐用年数は法定で47年とされていますが、実際にはそれ以上使用されるケースも多く見られます。
3. 気密性が高く、安定した居住環境を作れる
コンクリートは隙間が少なく、風や湿気の侵入を防ぐ性能があります。
そのため、外気の影響を受けにくく、カビや結露の発生リスクが低い室内環境を作りやすい点もメリットです。
1. 建築コストが高め
RC造は型枠工事・鉄筋工事・コンクリート打設など、多くの工程が必要です。
特に型枠の設置・解体やコンクリートの養生期間がコストに反映されるため、木造や軽量鉄骨造に比べて初期建築費が高額になりやすい傾向があります。
2. 工期が長くなりやすい
コンクリートは打設後、一定期間の養生が必要です。
この養生期間を短縮すると強度不足やひび割れの原因になるため、必然的に工期は長くなります。
また、施工現場での天候の影響も受けやすく、雨や低温時は打設作業が制限される場合があります。
3. 重量が大きく、地盤条件に制約がある
RC造は構造体の重量が大きく、建物全体の総重量も相当なものになります。
そのため、地盤が弱い土地では、地盤改良や杭基礎などの補強工事が必要になり、コスト増や設計制約が生じる場合があります。
SRC造は「Steel Reinforced Concrete」の略で、鉄骨の骨組みの周囲に鉄筋を組み、その全体をコンクリートで覆った複合構造です。
鉄骨の靭性(ねばり強さ)と鉄筋コンクリートの剛性・耐久性・耐火性を同時に活かせるため、安全性と安定性に優れています。
1. 耐震性が非常に高い
鉄骨は地震エネルギーを吸収するしなやかさを持ち、鉄筋コンクリートは建物の変形を抑える剛性を発揮します。
この組み合わせにより、大規模地震時でも構造体が倒壊しにくく、層間変形を小さく抑えられます。
また、揺れが長く続く長周期地震動にも耐えやすく、高層建物の安全性向上に寄与します。
2. 耐火性が高い
鉄骨がコンクリートで厚く被覆されるため、火災時の温度上昇が遅く、強度低下が起こりにくい構造です。
所定のかぶり厚を確保することで、法定の耐火時間を満たしやすく、安全性の維持に繋がります。
3. 高層建築に適した構造
大きな荷重や風圧、地震動に耐える強度を持ち、タワーマンションや超高層ビルに多く採用されています。
鉄骨の強度とコンクリートの剛性を活かすことで、細めの柱や梁でも高い安定性を確保でき、居住空間の有効利用がしやすくなります。
4. 長期耐久性に優れる
鉄骨がコンクリートに守られているため、湿気や塩害などの腐食要因から保護されます。
コンクリートの中性化やひび割れ幅を適切に管理すれば、数十年単位で安定した性能を維持することが可能です。
優れた性能を持つ一方で、複合構造ゆえに設計や施工が複雑になり、コストや工期が増加します。
1. 建築コストが非常に高い
鉄骨の製作、鉄筋の組立、型枠の設置、コンクリートの打設など、多くの工程が必要です。
各工程には高い施工精度と品質管理が求められるため、人件費や材料費がかさみます。
2. 工期が長い
鉄骨建方の後に配筋・型枠・コンクリート打設・養生といった手順を踏むため、工程が長くなります。
また、配筋密度が高いため、打設や締固めの作業に時間を要し、天候の影響も受けやすくなります。
3. 構造重量が大きい
RC部分が多いため建物の自重が大きく、基礎構造にかかる負担も増します。
地盤条件によっては、杭基礎や地盤改良など追加の基礎工事が必要となり、さらにコストと工期が延びる要因となります。
木造は柱や梁など主要な構造部材に木材を使用する構造で、日本の住宅や小規模アパートで広く採用されています。軽量で扱いやすく、伝統的な在来工法からツーバイフォー工法、集成材を用いた最新工法まで、幅広いバリエーションがあります。
1. 建築コストが安い
木材は鉄骨やコンクリートに比べて材料費が安く、加工も容易なため、施工の手間や工期を抑えられます。
特に在来工法では現場での加工や調整が柔軟に行えるため、設計の自由度を保ちつつコストを削減しやすい傾向があります。
2. 軽量で施工しやすい
木材は比重が軽く、搬入や組立が容易です。
建物全体の重量が軽くなるため、基礎や地盤への負担が少なく、地盤改良の必要がないケースも多く見られます。
また、プレカット(工場加工)を活用すれば精度の高い部材を短期間で現場に供給でき、工期短縮にもつながります。
3. 通気性が高く快適性がある
木材は自然素材ならではの調湿性を持ち、室内の湿度をある程度調整する働きがあります。
夏は蒸れにくく、冬は乾燥しすぎないため、住み心地の良い室内環境を作りやすい構造です。
また、木の手触りや香り、ぬくもりは心をほっとさせ、安心感を与えてくれます。
木造は他の構造に比べて耐久性や防火性能、防音性で劣る傾向があります。素材の性質を理解し、適切な施工や維持管理を行うことが不可欠です。
1. 防音性が低い
構造体が軽く、壁や床の質量も小さいため、上下階や隣室からの生活音が伝わりやすくなります。
防音性能を高めるには、二重床や二重壁、吸音材の充填、防振下地などの追加対策が必要です。
2. 耐火性が低い
木材は可燃性のため、火災時には構造体が燃え、強度が急速に低下します。
建築基準法の防火規定に従い、防火被覆や耐火ボード、石膏ボードによる覆いなどの対策が欠かせません。
3. シロアリや腐食のリスク
木材は湿気や虫害に弱く、シロアリ被害や腐朽菌による劣化が発生することがあります。
特に床下や浴室周辺などの湿気がこもりやすい箇所は注意が必要で、防蟻処理や換気計画、定期的な点検・補修が重要です。
建物の構造によって、丈夫さや地震への強さだけでなく、暮らしの中での「音の聞こえ方」も変わってきます。
上の階からの足音や、隣の部屋の話し声、外の車の音など…防音性能が低いと、思った以上に生活の快適さに影響します。
そこで、構造ごとのおおまかな防音性の目安をまとめました。
| 構造 | 防音性(遮音等級の目安) |
|---|---|
| SRC造 | ◎ 非常に高い |
| RC造 | ◎ 高い |
| S造 | ○ 中程度 |
| 木造 | △ 低め |
※この表はあくまで目安です。実際の防音性能は、壁や床の厚み、防音材の有無、施工の精度、窓やサッシの仕様などによっても変わります。

ここ数年、都市部のワンルームや投資用マンションではRC造(鉄筋コンクリート造)やSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)がほぼ主流になっています。
理由はシンプルで、「静かで長く住める物件が好まれるから」。
都心部の入居者は、仕事や生活の疲れを癒す“自分だけの空間”を重視する傾向が強く、防音性の高さはかなり重要なポイントです。
RCやSRCは遮音性能に優れていて、隣や上下階からの音が伝わりにくく、結果的に退去理由の上位に入りやすい「音のストレス」を減らせます。
さらに、耐久性・耐火性が高く、見た目や設備が古くなっても建物自体の安心感は長く保たれるため、築年数が経っても一定の賃料を維持しやすいのも大きな強みです。
一方、地方や郊外では事情が少し違います。
車移動が前提のエリアや、家賃重視の層が多い地域では、S造(鉄骨造)や木造の低層アパートにも根強い需要があります。
初期投資を抑えつつ駐車場付きの広めの間取りを提供できるため、学生やファミリー層にも選ばれやすいです。
結局のところ、構造の選択は「誰に貸すか」「どこに建てるか」で変わります。
都市部のワンルーム投資ならRC造が安定路線、郊外や地方での長期賃貸経営ならS造や木造も戦略に組み込む価値があります。
入居者のニーズに合った構造を選べば、空室リスクを抑えて安定経営につなげやすくなります。

投資用マンションの収益性や安定度は、立地と構造の組み合わせで大きく変わります。
同じエリアでも、構造が違えば入居者層や賃料水準、空室リスクまで変わってくるため、購入前にしっかり検討することが大切です。
1. 立地+構造で需要が決まる
交通アクセスが良く人口流入の多いエリアでは、静かで安心感のあるRC造やSRC造の人気が高めです。
逆に郊外や地方では、駐車場付き・家賃控えめなS造や木造が選ばれる傾向があります。
2. 入居者層に合わせた構造選び
防音性や耐震性を重視する単身者・ファミリー層が多いエリアではRC造・SRC造が有利。
一方、高利回りを狙うなら、初期費用を抑えられるS造・木造も検討の余地があります。
3. ランニングコストの違いを把握する
修繕費や火災保険料は構造によって変わります。
耐久性の高い構造は修繕周期が長い反面、初期費用が高くなりがちです。逆に木造や軽量鉄骨は初期費用は安くても、修繕やメンテナンスの頻度が多くなる場合があります。
4. 長期の収支シミュレーションが必須
購入時の価格だけでなく、10年・20年先の修繕や維持管理費、賃料変動を見込んだシミュレーションを行うことが、安定経営の鍵となります。
構造の違いは、入居率・家賃設定・維持管理コスト・将来の売却価格に直結します。
投資用マンションを長期で運用するなら、それぞれの構造のメリット・デメリットを正しく理解し、立地やターゲット層に合った選択をすることが重要です。
「なんとなく」で構造を選ぶのではなく、数字と需要を踏まえて判断することが、安定した不動産投資の第一歩です。

\オークション査定で投資用マンションをかしこく売却/
営業電話に悩まされず、スピーディーに売却を進められます。
「損をせずに手放したい」「売却がなかなか進まない」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。