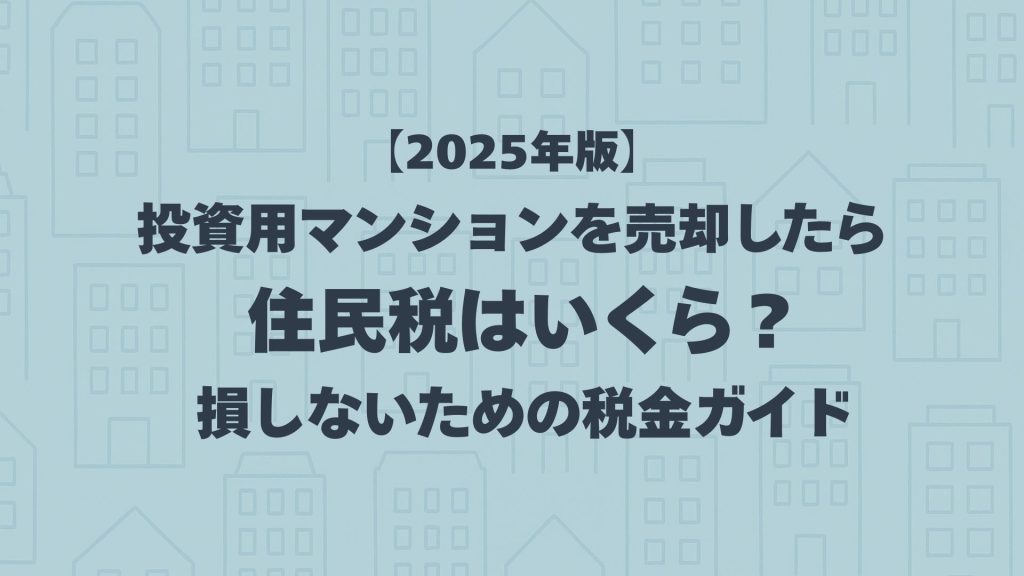
「投資用マンションを売ったら、どのくらい住民税がかかるの?」「そもそもいつ支払うの?」 そんな疑問をお持ちではありませんか?
この記事では、投資用マンションの売却で発生する住民税の仕組みと、節税のポイントについてわかりやすく解説します。税金で損をしないためにも、売却前に必ずチェックしておきましょう。
マンションを売却して利益(譲渡益)が出た場合、それは「譲渡所得」として課税対象になります。この譲渡所得に対しては、所得税と住民税、そして復興特別所得税がかかる仕組みです。
これらの税金は、翌年の確定申告で申告することにより、税額が確定します。特に住民税は、売却した年の所得をもとに翌年課税される「前年課税方式」が取られており、実際の納付は翌年の6月以降になります。
譲渡所得にかかる住民税の税率は、一律5%です。これに対し、所得税は保有年数によって異なり、短期と長期で次のように税率が変動します。
| 項目 | 内容 | 税率 |
|---|---|---|
| 所得税(短期譲渡) | 5年以下の所有期間 | 30% |
| 所得税(長期譲渡) | 5年超の所有期間 | 15% |
| 住民税 | 短期・長期共通 | 5% |
| 復興特別所得税 | 所得税に対して加算 | 約0.315% |
上記の通り、住民税は譲渡益が出た場合には必ず課税されますが、給与や年金などのほかの所得がある場合、譲渡損失があったとしてもそれらの所得に対しては通常通り住民税が課税されます。
このため、「譲渡損失がある=住民税がゼロになる」と単純に考えるのは危険です。不動産売却による住民税の有無と、その他所得に対する住民税の課税は別々に計算されるため、正確な理解が必要です。

不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して税金が課されます。譲渡所得の金額は以下の式で計算されます。
この式を正しく理解することが、余計な税負担を避ける第一歩です。
取得費とは、売却する不動産を購入した際にかかった費用のことです。主な内訳は以下の通りです。
注意点として、購入当時の資料(契約書や領収書)が手元にない場合は「概算取得費」として売却価格の5%で計算される可能性があります。
この場合、実際に支払った金額より取得費が少なく見積もられ、結果として課税対象額が増える点に要注意です。
不動産売却時にもさまざまなコストがかかります。これらも譲渡所得から差し引くことができます。
これらの費用についても、必ず領収書や請求書を保管しておきましょう。証明資料がなければ、経費として認められない可能性があります。
譲渡所得からさらに差し引くことができるのが、特別控除です。代表的なものとして「3,000万円特別控除」がありますが、これは次の条件を満たした場合に限られます。
なお、この控除は「投資用マンション」には原則として適用されません。賃貸に出していた場合や居住実績のない物件は対象外です。
しかし、過去に一定期間以上自己居住していた実績があり、売却時にその要件を満たす場合には、例外的に控除の適用が認められるケースもあります。
その可否は複雑な判断が必要になるため、該当の可能性がある場合は専門家(税理士)に相談することをおすすめします。
以上の3つの項目「取得費」「諸経費」「特別控除」を正しく理解し、証明資料をしっかり準備することで、適切な課税額を導き出すことが可能です。

投資用マンションを売却した翌年に確定申告を行うと、その内容をもとに各自治体が住民税を計算します。
住民税は、原則として6月から納付が始まり、4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて支払う方式です。一括払いも可能です。
住民税の徴収方法には、大きく分けて「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
なお、投資用マンションの売却によって想定以上の譲渡益が出た場合、翌年の住民税が大きく跳ね上がる可能性があります。
そのため、売却益を全て使い切らず、あらかじめ住民税や所得税などの納税資金を確保しておくことが極めて重要です。
特に普通徴収の場合は「突然の高額請求」に備える必要がありますので、資金繰りには十分な余裕を持たせましょう。し、資金繰りが苦しくなることも。売却代金の一部を税金支払い用に確保しておくことが大切です。

税金は正しい知識を持つことで、合法的に抑えることが可能です。ここでは、特に住民税の節税に役立つ代表的な方法を詳しく紹介していきます。
投資用マンションの売却で得た譲渡益は「分離課税所得」として扱われます。これにより、他の譲渡所得と損益を相殺(損益通算)することができます。
たとえば、以下のようなケースが考えられます
<通算できるケース>
ただし、損益通算ができるのは「同じ税区分」内に限られます。つまり、不動産譲渡益は不動産譲渡損失としか通算できません。株やFXなどの損失とは通算できないため注意が必要です。
<通算できないケース>
(※)株式など「分離課税」の中でも異なる区分にあるため
これらの計算は複雑になりがちなので、税理士のアドバイスを受けることで確実な節税につながります。
投資用マンションを売却する場合、保有期間によって課税される税率が大きく異なります。
住民税については一律となりますが、所得税率の違いが大きいため必ず把握しておきましょう。
| 譲渡所得の種類 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 5% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |
このように、長期所有の方が所得税率が半分になるため、節税効果が非常に大きくなります。
注意点として、「5年を超える」とは、単に5年経過したことではなく、「売却した年の1月1日時点で取得から5年超」であることが条件です。
たとえば2019年4月に購入した場合、2025年1月1日までは短期譲渡扱いとなるため、売却タイミングの調整が節税の鍵となります。
また、長期譲渡でも一定の要件を満たすと「軽減税率の特例」が使えることがあります。居住用財産に限定されますが、仮に一部居住していた場合など、可能性がある方は税理士に確認してみましょう。
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすることで、翌年の住民税や所得税から一部が控除される制度です。
実質的な自己負担額はわずか2,000円で済み、多くの自治体が魅力的な返礼品を用意していることから、非常に人気を集めています。
ここで注意したいのは、「その場で住民税が減る」のではないという点です。
実際には、今年中に行った寄付額が、翌年の住民税や所得税から差し引かれる仕組みとなっています。
つまり、ふるさと納税は「翌年に控除される前払い型の制度」と理解するとわかりやすいでしょう。
投資用マンションの売却で大きな譲渡益が出た年は、その年の所得が増えるため、ふるさと納税の寄付上限額も広がります。
このタイミングで寄付を活用すれば、より多くの控除を受けることができ、翌年の住民税や所得税の負担を軽くすることにつながります。
なお、ふるさと納税による控除は「その年の所得」に基づいて計算されるため、寄付は売却年のうちに済ませておく必要があります。
ワンストップ特例制度を使えば確定申告なしで寄付の手続きが可能ですが、譲渡益がある年は確定申告が必要となるため、ふるさと納税の控除も通常の確定申告で行いましょう。
ふるさと納税を上手に活用すれば、税負担を軽減しながら地域貢献にもつながる、まさに一石二鳥の制度です。
賢く使えば、節税以上の価値を感じられるはずです。
A. いいえ。売却した年には反映されません。住民税は前年の所得に対して課税されるため、売却した翌年に増額されます。
A. 確定申告をしないままでいると、税務署からの調査対象になり、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。
A. はい。譲渡損失が出た場合は、住民税も課税されません。ただし、必ず確定申告を行い「損失が出た」ことを申告しなければゼロになりません。
A. 控除や損益通算は複雑なので、不安があれば税理士に依頼しましょう。正確な処理ができるだけでなく、余計な税負担を回避できます。

投資用マンションの売却では、住民税を含めた税金の知識が不可欠です。税負担は無視できない額になることも多いため、しっかりと準備をしてから売却に臨むべきでしょう。
特に、確定申告や住民税の納付時期を見落としてしまうと、後になって思わぬ出費に悩まされる可能性もあります。譲渡所得の計算や特例適用の有無など、少しでも迷ったらプロに相談するのがおすすめです。
税金の知識を武器に、より有利な不動産取引を目指していきましょう。
\オークション査定で投資用マンションをかしこく売却/
営業電話に悩まされず、スピーディーに売却を進められます。
「損をせずに手放したい」「売却がなかなか進まない」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
