
不動産投資を行う上で、「いつ売却するか」という判断は非常に重要です。特に投資用マンションでは、購入時の価格や立地だけでなく、売却タイミングが成功の鍵を握ります。
大阪・京都・神戸といった関西エリアでは近年、中古マンションの価格上昇が続いており、高値売却のチャンスを狙う投資家も増えています。
本記事では、初心者の投資家の方に向けて、「投資用マンションの売り時」を見極めるための3つのポイントを解説します。
さらに、統計データや不動産の専門家の見解も取り入れ、深掘りしていきます。
ぜひ最後までお読みいただき、ご自身の資産運用にお役立てくださいね。

投資用マンションを売却する際は、まず自分の物件があるエリアの不動産市場の動きをチェックしましょう。
特に大阪市では再開発やインバウンド回復の影響により、2024年の中古マンション平均価格は前年比6.2%の上昇を記録。
京都市でも観光地周辺の需要が堅調に推移しており、ワンルームマンションの平均成約価格は前年より4.8%上昇しました。神戸市では湾岸エリアの開発が進み、単身者向け物件の人気が高まりつつあります。
このようなエリア別の価格動向を確認し、「自分の物件が属する地域では価格が上がっているのか?」「この流れがいつまで続くのか?」を判断することが、売却の成功率を高める第一歩です。
不動産価格は、需要(買いたい人)と供給(売りたい人)のバランスで決まります。
需給バランスは地域ごとに大きく異なり、2024年の近畿圏全体では中古マンションの成約件数が前年同月比+5.9%と堅調に推移。売り出し物件の在庫数は微減傾向で、買い手優位から売り手優位へと移行しつつあります。
つまり、買い手が活発に動きつつある今こそ、売却を検討する価値があるタイミングだといえるでしょう。
投資用マンション市場では、金利の動向が投資家の購買行動や不動産価格に大きな影響を与えます。
特に投資ローンの金利は、物件の収益性やキャッシュフローに直結するため、売却を検討する際の重要な判断材料になります。
現在、都市銀行では不動産投資ローンの金利が年1〜2%台、地方銀行や信用金庫では2%台後半が一般的です。
日本政策金融公庫のような一部機関では1〜2%台の低金利も見られますが、審査基準は厳しめです。対して、ノンバンク系では3%前後の金利が主流で、やや高めながら融資の柔軟性が魅力です。
こうした低金利環境下では、ローンを活用する投資家が物件を購入しやすいため、売却側にとっては需要が高まる追い風となります。
とくに利回りの高い物件は人気が集中しやすく、好条件での売却も期待できます。
一方で、今後金利が上昇局面に入ると、買い手側の資金調達コストが上昇し、収益性の低下から購入意欲が鈍るリスクがあります。
さらに、融資審査の厳格化や借入可能額の縮小により、買い手の裾野が狭まり、不動産価格が下落傾向に転じる恐れもあります。
景気の影響も見逃せません。景気拡大期には投資マインドが高まり購入意欲が強まりますが、不況期には将来の収益不安から買い控えが起こり、売却にも時間がかかるようになります。

適切な売出価格の設定は、高値売却を成功させるうえで欠かせません。相場とかけ離れた高すぎる価格では売れ残ってしまい、かといって安すぎれば利益を逃します。
そこで、この章では投資用ワンルームマンションの価格相場を調査する方法を解説します。複数の情報源を駆使して客観的な相場観を掴み、戦略的に売却価格を決めましょう。
投資用マンションを売却する際には、まず相場を把握することが大切です。
不動産会社に査定を依頼するのが一般的で、特に近年では不動産一括査定サイトの利用が広まっています。一括査定を使えば、複数の不動産会社から査定結果を一度に取得できるため、効率よく比較検討できるというメリットがあります。
しかし一方で、「営業電話が多い」「価格がバラバラでどれを信じればいいのかわからない」といった悩みを抱える方も少なくありません。
そこで注目されているのが、ReTrue(リトゥルー)という新しいスタイルの査定サービスです。
ReTrueは従来の一括査定とは異なり、オークション形式で複数の買主企業や投資家から入札を募る独自の仕組みを採用しています。
これにより、物件の市場価値を正当に評価でき、より高値で売却できる可能性が高まります。
さらに、ReTrueでは買主企業とのやり取りをすべて一括管理してくれるため、営業電話ゼロのストレスフリーな査定が実現。オーナーは結果を待つだけで、手間なく効率的に売却活動を進めることができます。
▶ 詳しくはこちら ReTrueの詳細を見る
次に、自分でも市場の売出事例を調べてみましょう。
不動産ポータルサイト(SUUMOやHOME’Sなど)を活用して、自分の物件と「同じエリア」「築年数」「広さ・間取り規模」が近いマンションが、現在どの程度の価格で売りに出されているのかを検索してみてください。
2024年4月時点の調査では、大阪市内のワンルームマンション(築15〜20年)の売出価格は平均1,680万円前後で推移しています。これにより、「自分の物件はおおよそこの価格帯で売れそうだな」といった相場感を把握することができます。
ただし注意点として、ポータルサイトに掲載されているのは「売主の希望価格」であり、必ずしも実際にその価格で成約しているとは限りません。多くの場合、多少高めに価格を設定し、値下げ交渉を前提としているケースもあります。
また、賃貸中の投資用マンション、いわゆる「オーナーチェンジ物件」の売出価格も確認しておくとよいでしょう。入居者が付いた状態かどうかによって、利回りや収益性の評価が変わり、結果として売却価格にも影響を与えます。
さらに、周辺の賃料相場も同時にチェックしておくと、投資物件としての魅力や利回りを判断する材料になります。
ポータルサイトは情報量が豊富なため、時間をかけて類似物件のデータを丁寧に集めることが、適切な価格設定と売却戦略の第一歩となります。
市場の民間情報だけでなく、国や自治体が公表している公的価格データも非常に参考になります。代表的なものに「公示地価」や「路線価」があります。
「公示地価」は国土交通省が毎年公表している標準的な土地価格で、不動産売買の目安となります。一方、「路線価」は国税庁が公表している土地評価額で、相続税や贈与税の算定基準として使われるものです。
マンションは建物と土地の複合資産であるため、これらの価格指標を活用して土地部分の価値を概ね把握することができます。なお、路線価は一般的に公示地価の約80%程度とされています。
さらに、国土交通省の「土地総合情報システム」では、不動産取引価格情報検索が可能で、過去に実際に取引された物件の情報(所在地・面積・取引価格・築年数など)を閲覧することができます。
たとえば「○○駅徒歩5分、築15年、50㎡前後のマンションが直近でいくらで取引されたか」といった情報は、相場の裏付けとして非常に有効です。
このように、公的データを活用することで、より信頼性の高い価格設定が可能になります。民間の売出価格とあわせて確認し、根拠のある売却価格を設定することが成功の鍵になります。

投資用マンションの売却を判断する際、悩ましいのが「売るべきか、このまま保有すべきか」という問題です。
つまり、物件を手放して得られる売却益と、持ち続けた場合の家賃収入とを比較してどちらにメリットがあるかを見極める必要があります。
この章では、家賃収入と売却価格のバランスを考えるうえで知っておきたいポイントを解説します。
売却益と家賃収入のバランスを考える際には、キャッシュフローと利回りの両方を計算しましょう。
まず現在の物件から得られている年間の純利益を計算してみましょう。毎月の家賃収入×12ヶ月分から、経費(管理費・修繕積立金、固定資産税、賃貸管理会社への手数料、ローン金利分など)を差し引きます。この純粋な手取り収入が、その物件を保有し続けることで毎年得られる利益です。
次に、現在その物件を売却すると手取りでいくら残るか(査定価格-残債務-諸経費)を試算します。そして、それが今後の何年分の家賃収入に相当するかを考えてみてください。
この場合、2,000万円 ÷ 66万円 ≒ 約30年分の家賃収入に相当します。
さらに、あるマンションのケースでは、売却によって諸費用差引後で約7,600万円の手取りが見込まれ、月額家賃20万円で保有し続けた場合には同額を得るのに約32年、25万円でも約25年かかる計算となりました。
25~30年分の将来家賃を、いま一括で受け取れると考えれば、売却のメリットが非常に明確になります。
もちろん将来の家賃下落や空室リスク、修繕費増加といった変動要因も考慮すべきですが、「このまま◯年間運用し続けるのと、今売るのとではどちらが得か?」を数字で比較することは、極めて重要な判断材料となります。
場合によっては今のうちに売却して利益を確定させる方が、将来的な不確定リスクを回避できるという結論になることもあります。
不動産投資の醍醐味は、安定した家賃収入を長期間得られることにあります。長期保有を選ぶことで、毎月の家賃収入を積み重ねながら将来的な物件価値の上昇を期待することができます。
特に都心部や人気エリアの物件では、資産価値が維持されやすく、長期的に見て売却益がさらに拡大する可能性もあるでしょう。
また、長期保有には節税のメリットもあります。減価償却を毎年経費として計上することで不動産所得を圧縮し、結果的に税負担を軽減できるため、毎年のキャッシュフローが安定しやすくなる点も見逃せません。
一方で、デメリットも無視できません。築年数が経過するほど、外壁や配管、エレベーターなどの大規模修繕が必要になる可能性が高くなり、修繕コストが増加します。
さらに、古くなった設備の更新や法令対応(耐震性、消防設備など)にも追加コストがかかることがあります。
また、築年数が進むことで物件の魅力が低下し、入居者が付きにくくなるケースも増えてきます。空室リスクが高まると収入が不安定になり、利回りにも大きく影響します。
実際、専門家の間では「築年数が古くなる前に売却することで、空室や修繕リスクの高まりを回避し、安定した投資成果を確保できる」との意見もあります。加えて、減価償却期間が終了すると経費として計上できる額が減り、税負担が逆に増えてしまう点にも注意が必要です。
たとえば、木造アパートは法定耐用年数が22年、RC造の区分マンションでは47年と定められており、この期間を過ぎると減価償却による節税効果がなくなってしまいます。
このタイミングを一つの区切りとして、売却を検討するのも賢明な判断といえるでしょう。
こちらの記事もおすすめ!
▶ワンルームマンションは長く保有するべき?売却のタイミングや保有期間ごとの戦略を解説
保有しているマンションの家賃が周辺相場より高く設定されている場合、それをどこまで維持できるかも重要な検討材料になります。
相場家賃が下落傾向にあるエリアでは、利回りの悪化や将来的な値下げリスクを見据え、早めの売却を視野に入れるべきです。
逆に、賃料が安定しており、相場より高めの水準で推移している場合には、その物件が高収益物件として投資家に魅力的に映るため、売却時に高値で取引されやすくなるメリットもあります。
こうした観点を踏まえると、売却を検討すべきタイミングもより明確になります。
例えば、以下のような状況が売り時のサインとなるでしょう
実際、家賃が相場より高く安定している物件は、投資家にとって「即時に利回りが見込める物件」として魅力が高く、購入意欲を刺激しやすいため、売却価格にも好影響を与える可能性が高まります。
このように、自分の物件を取り巻く家賃水準・市況・税制などの変化を冷静に捉えて、「今売るべきか、持ち続けるべきか」を見極めていくことが大切です。

投資用マンションを売却して利益(譲渡所得)が出た場合、税金のことも考慮しなければなりません。せっかく高く売っても、後で思った以上に税金で引かれてしまった…ということがないよう、基本的な税金知識と節税ポイントを押さえておきましょう。
投資用マンションを売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益には所得税と住民税が課税されます。これらをまとめて「譲渡所得税」と呼び、税率は物件の所有期間によって大きく異なります。
この「5年超」の判定は、売却した年の1月1日時点での所有期間で判断されるため注意が必要です。
たとえば2016年6月に購入した物件を2021年10月に売却しても、2021年1月1日時点で所有期間が5年未満となるため、短期譲渡扱いになります。
実質的に「丸6年以上保有」しないと長期譲渡にならない点に注意しましょう。
仮に譲渡益が1,000万円出た場合、短期譲渡なら約396万円、長期譲渡なら約203万円の税金がかかります。
その差はおよそ193万円にもなるため、保有年数による税率の違いは売却判断において非常に重要です。売却タイミングを決める際には、所有年数による税率の違いを必ず確認しましょう。
①長期譲渡の適用を狙う
売却を検討している物件が、まだ5年未満の所有であれば、できるだけ「長期譲渡所得」になるまで待つことで税率を約半分に抑えることができます。
②特例制度の確認
投資用マンションには原則として適用されませんが、もし過去に自分や家族が居住していた物件を賃貸に出していた場合、以下のようなマイホーム向け特例が適用できるケースがあります。
これらは条件や制限が細かいため、適用可否については必ず税理士や不動産会社に事前に確認することが重要です。
税金以外にも、売却にかかる費用が手取り額に影響します。主な費用項目は以下のとおりです。
①仲介手数料
売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税が上限です。
例えば3,000万円で売却した場合、3,000万円 × 3%(90万円)+ 6万円 = 96万円、消費税を加えると約105.6万円(税込)となります。
ただし、ReTrue(リトゥルー)ならこの仲介手数料が0円。
通常は大きな負担となる手数料をカットできるため、売却益がそのまま手元に残るのが大きなメリットです。「費用を抑えて売りたい」「手取りを最大化したい」といった方には、非常に魅力的な選択肢です。
▶ 詳しくはこちら ReTrueの詳細を見る
②印紙税
売買契約書に貼る印紙代で、契約金額に応じて税額が異なります。おおよそ1〜3万円程度で、現在は軽減措置が適用されている場合があります。
③登記費用
抵当権抹消登記や所有権移転登記などにかかる費用。司法書士への報酬を含めて1万〜3万円程度が目安です。
④ローンの繰上返済手数料
ローンが残っている場合、金融機関によっては繰上返済に数千円〜数万円の手数料が発生することがあります。契約内容によって異なるため、事前に確認が必要です。
仲介手数料などは経費として譲渡所得から控除できますが、現金の手取り額としては確実に差し引かれます。これらを踏まえて「税引き後の実質手取り額」を試算することが、後悔しない売却につながります。
特に短期譲渡では税率が高いため、諸費用や税金を引くとほとんど手元に残らないケースもありえます。事前に十分なシミュレーションを行い、納得のいく形で売却を進めましょう。
マンション売却の費用についてはこちらの記事もどうぞ!
▶投資用マンションを売却する際の費用一覧と節税方法|手元に残る利益を最大化するコツ
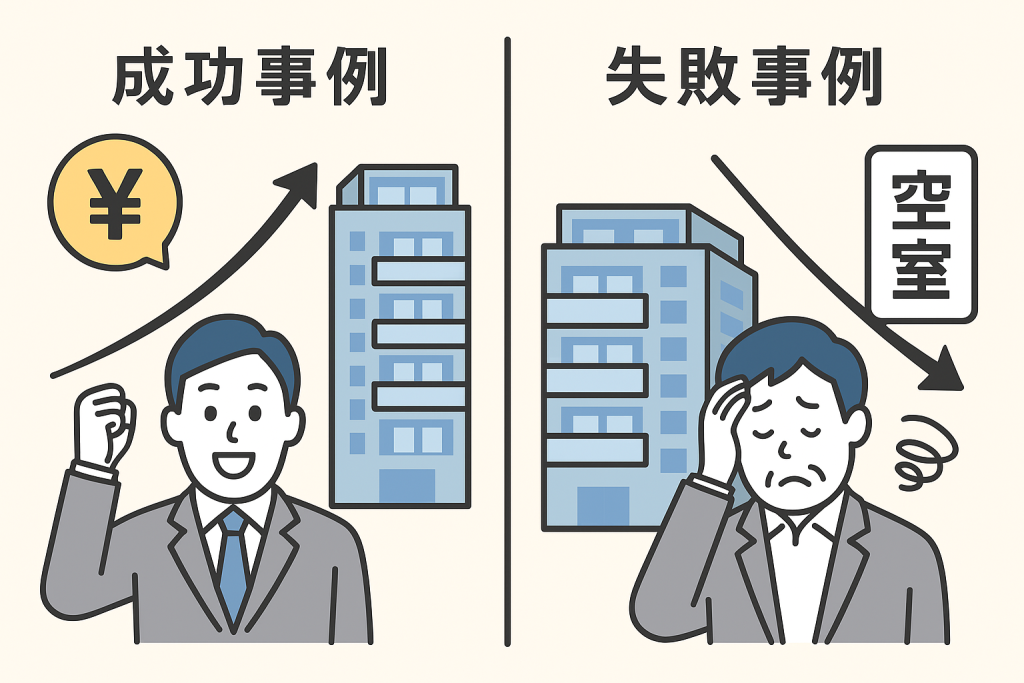
実際の成功例や失敗例から、最適な売却タイミングの重要性を再確認してみましょう。ここでは投資用マンションの売却で高い成果を上げたケースと、残念ながら失敗してしまったケースを1つずつ紹介します。
京都市に住むKさんは、築34年のワンルームマンションを所有していました。
「投資用としての需要があるうちに売却しよう」と考え、複数の不動産会社に査定を依頼。6社から提示された査定額には約200万円の差がありましたが、金額だけでなく提案内容や信頼性を比較検討した結果、大手仲介会社に依頼を決断しました。
結果として、購入時と同額での売却に成功。築年数が経過していても「投資用としての需要が見込める」と的確に判断し、戦略的に行動した好例です。
このケースのポイントは、複数の査定を比較し、専門的なアドバイスをもとに行動したこと。Kさんは長年の家賃収入を得たうえで、資産を高値で売却することに成功しました。
一方、東京都内に住むTさんのケースです。将来の資産形成を目的に、都内でワンルームマンションを購入し、賃貸運用を始めました。
当初は入居者が付き順調な運用でしたが、途中で退去が発生し、家賃収入が途絶えてしまいます。
さらに、購入価格が割高であったことが発覚。ローン返済の負担が大きくなり、キャッシュフローが悪化した結果、やむを得ず売却を決断。不動産投資は断念することになりました。
この失敗は、物件選定と資金計画の甘さが原因です。「利回りに無理がある物件を選ばない」「空室リスクを過小評価しない」といった基本を守ることの重要性がよくわかる事例です。
成功例と失敗例を比べると、明暗を分けたポイントが浮かび上がります。
成功したKさんは市場ニーズに合ったタイミングで売却し、専門家の力を借りて最善の戦略をとりました。失敗したTさんは市場タイミング以前に収支計画の甘さから投資プラン自体が破綻してしまいました。
投資用マンションでは「いつ売るか」も重要ですが、その前提として「適正な価格で買う」「無理のないローンを組む」「空室対策を怠らない」ことが不可欠です。
例えば、売却時には可能な限り空室を埋めてから売りに出すのが望ましいと言われます。
入居者が付いて家賃収入が確保されている物件は、購入後すぐに収益を得られるため投資家にとって魅力的であり、空室のまま売るより高く売却しやすいからです。
逆に空室のまま長期間売りに出してしまうと、その間の機会損失に加え「なかなか借り手が付かない物件」という印象を与え、結果的に値下げせざるを得なくなるリスクもあります。これは多くのオーナーが経験する失敗パターンなので注意しましょう。
また、価格交渉の対応も成否を分けます。強気に構えすぎてチャンスを逃したり、逆に安易に値下げしすぎたりしないよう、プロの助言を仰ぎつつ適切に対応することが大事です。成功事例・失敗事例から得られる知見を活かし、自分の売却でもベストな結果を目指しましょう。
不動産会社の担当者によると、以下のようなタイミングが売却の好機とされています。
国土交通省の不動産価格指数によると、2023〜2024年にかけて区分所有マンションの価格は全国平均で前年比6.8%上昇しています。特に近畿地方では大阪市の価格上昇が全国平均を上回っており、投資用マンションの売却には好環境が続いています。
このような公的データや市場の動きを冷静に把握することが、失敗しない売却の第一歩です。

最後に、不動産のプロが提唱する「ベストな売却タイミング」の考え方をご紹介します。経験豊富な専門家たちの知見は、売却時期を見極めるうえで非常に参考になります。
1.築年数
マンションは築10〜20年程度が売却適齢期とされます。それ以降になると買い手が付きにくくなる傾向があります。築浅すぎても価格が高く、利回りが低くなるため敬遠されることも。
2.所有期間
5年超であれば長期譲渡所得の対象となり、税率が大幅に下がります。この「税制上の節目」は多くの投資家が意識しているポイントです。
3.金利の動向
低金利は買い手のローン負担が軽く、購入意欲が高まりやすいため、売却には追い風です。金利上昇が始まる前に動くことが重要とされています。
4.季節要因
1〜3月は不動産の繁忙期。売却の準備は11〜12月から始めるのが理想的です。早めに市場に出すことで、競合より優位に立てる可能性があります。
5.地域市況
エリアに新駅開業や再開発などのプラス要素がある場合はチャンスです。逆に景気後退や税制改正などのマイナス要因が見えたら、早めの売却が有利となります。
ある不動産アナリストは「需要が供給を上回る時期に売ることが高値売却のコツ」と語ります。市場に競合物件が少なく、買い手が活発なタイミングを狙えば、強気の価格設定でも成立しやすいでしょう。
また別の専門家は「勘ではなく、データに基づいた判断が大切」と強調します。価格指数や成約件数の推移といった客観的な指標をチェックし、売却時期の判断材料にすることが重要です。
実際に、2008年から2024年にかけて区分所有マンションの価格は全国的に上昇傾向を維持しており、今が売り時である可能性もあります。
不動産投資に成功している人たちは、「欲を出しすぎないこと」を鉄則としています。「もっと上がるかも…」と売却を先延ばしにしているうちに市況が冷え込み、結果的に値下げせざるを得なくなったという事例も多く聞かれます。
一方で、「◯年保有して◯円値上がりしたら売却する」といった明確なルールを持つ投資家は、冷静に利益確定し、次の投資に進んでいます。これは初心者にとっても非常に有効な考え方です。
また、プロの投資家は売却の際に複数の専門家から意見を聞いています。不動産仲介会社や不動産コンサルタントなど、異なる視点を取り入れることで、より客観的で精度の高い判断ができるからです。
市場動向、物件の状態、自身の資産計画という「3つの視点」が重なったタイミングこそ、ベストな売り時です。どれか一つでも大きな懸念材料があるなら、無理に売却せず見送る判断も必要です。
不動産はタイミングが命です。常に情報を収集し、準備を怠らなければ、最適な売却のチャンスは必ず訪れます。その好機を逃さず、より良い投資成果につなげていきましょう。
こちらの記事もおすすめ!
▶投資用マンションの出口戦略とは?ワンルーム売却で後悔しないための基礎知識
投資用マンションの売却で後悔しないためには、以下の3つの観点からしっかりと判断することが重要です。
そして、迷ったら専門家に相談し、複数の意見を取り入れて判断を下すことも重要です。焦らず、しかしチャンスは逃さず。投資の出口戦略として、最適な売却タイミングをつかんでください。

ReTrueの最大の特長は、独自のオークション形式による査定です。
「オークション査定って何だろう?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、一括査定とは異なり、物件ごとにオークション形式で買主企業や投資家から入札を募る独自の仕組みです。
従来の査定方法では、一部の不動産会社が買主を探す形が一般的でしたが、ReTrueでは100社以上の買主企業に対して入札を募る仕組みを採用しています。
この方法により、物件の市場価値が適切に評価され、オーナー様にとって最大限の利益を引き出すことが可能です。
通常、不動産売却では売却額の3%程度の仲介手数料が発生します。しかし、ReTrueではこの手数料を完全にカット。これにより、売却益がそのままオーナー様の手元に残ります。
これは、費用対効果を重視するオーナー様にとって大きな魅力です。
従来の一括査定では、複数の不動産会社から頻繁に営業電話やメールが届くケースが多く、オーナー様の負担となっていました。
ReTrueでは、買主企業とのやり取りをすべて弊社が一括管理するため、こうしたストレスから解放されます。オーナー様は売却の進捗を安心して見守るだけです。
ReTrueでは、投資用マンションの売却に特化したプロフェッショナルがオーナー様をサポートします。市場調査をもとにした販売計画の立案、入札プロセスの管理、契約書類の準備など、売却に関するすべてのステップを安心してお任せいただけます。
また、税務や法務のアドバイスも提供しているため、初めて売却を行う方でもスムーズに取引を進めることが可能です。
▶ 詳しくはこちら ReTrueの詳細を見る