
「もし自分に何かあったら、家族に迷惑をかけてしまうのでは…」
そう考えたことがある不動産オーナーは少なくありません。実は、不動産投資ローンに付帯する団体信用生命保険(団信)が、この“もしも”の備えとして機能することをご存じでしょうか。
団信に加入していれば、契約者に万が一のことが起きてもローンは完済扱いとなり、物件を「借金のない資産」として家族に残すことができます。
この記事では、不動産投資が生命保険の代わりになる理由と注意点を、実際の仕組みや具体例を交えてわかりやすく解説します。
“資産を残す考え方”を見直すきっかけとなる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
\オークション査定で高値売却を実現/
複数の不動産会社が同時に入札する「オークション形式」で、最も高い査定を提示した会社をご紹介します。営業電話もなく、スムーズに比較検討できる安心の仕組みです。
「損をせずに手放したい」「信頼できる会社に任せたい」という方は、まずは無料査定からお試しください。
ReTrueの無料査定を試す不動産投資と生命保険、一見まったく異なるものですが、「家族の将来を守る」という目的は共通しています。
多くの人が生命保険を検討する理由は、突然の病気や事故で収入が絶たれたとき、残された家族の生活を支えるためです。
一方、不動産投資のローンには団体信用生命保険(団信)が付帯しており、もし契約者が亡くなった場合、保険金でローン残高が一括返済されます。
つまり、「住宅ローンがゼロになった状態で不動産が残る」ため、家族はその物件を売却して現金化したり、家賃収入を得たりできます。
この仕組みが「不動産投資は生命保険の代わりになる」と言われる理由です。
ただし、この“代わり”には限界があります。団信はあくまでローン返済不能リスクに備える保険であり、生活費や教育費などの日常的な支出まではカバーしません。
その違いを理解したうえで、不動産投資と生命保険のバランスを考えることが大切です。

不動産投資でローンを組む際、多くの金融機関が加入を求めるのが「団体信用生命保険(団信)」です。
これは、契約者が死亡または高度障害などで返済不能になった場合、保険金でローンを完済する仕組みの保険です。
つまり、団信は「ローン返済不能リスク」に備える保険であり、契約者の生命に万一のことが起きた際に、家族がローンを背負うことなく不動産を資産として残せるという特徴があります。
ここでは、団信の加入タイミングから保険金の流れ、保険料の仕組み、そして保障内容の種類までを詳しく見ていきましょう。
団信は、不動産投資ローンを契約するときに原則として同時加入します。
金融機関がローン契約の条件として団信を必須にしていることが多く、
住宅ローンと同様に「融資実行=団信契約スタート」となるのが一般的です。
このため、申込み時に健康状態を告知する必要があり、持病がある場合には加入を断られることもあります。
その場合、健康上の理由で一般の団信に入れない人向けに「ワイド団信」や「引受緩和型団信」と呼ばれる商品が用意されています。
審査の柔軟性は金融機関によって異なりますが、金利が0.2〜0.3%ほど上乗せされるケースが一般的です。
また、契約後に団信だけを途中で追加することは難しいため、加入は融資契約のタイミングが唯一の機会と考えておきましょう。
団信の保険金は、一般の生命保険と異なり「遺族」ではなく「金融機関」が受け取ります。
仕組みとしては次の通りです。
①契約者が死亡または高度障害状態になる
②保険会社が、残っているローン残高に相当する金額を金融機関に支払う
③金融機関がその保険金でローンを完済扱いとする
この流れにより、借入残高が0円となり、家族には「借金のない状態の不動産」が残ります。
たとえば、3,000万円の投資用マンションをローンで購入していた場合、契約者に万一が起きても、
団信が発動すれば家族にはローンのないマンションがそのまま相続されます。
その後、家族は
①物件を売却して現金化する
②賃貸経営を継続して家賃収入を得る
のどちらかを選べます。
このように団信は、家族に負債ではなく資産を残す仕組みとして機能するのです。
団信の保険料は、通常の生命保険のように別途支払うものではありません。
ローン金利に上乗せされているため、返済額の中に保険料が含まれています。
たとえば、借入金利が2.0%のローンで、団信を付けると2.2%になる場合、
その0.2%分が団信の保険料に相当します。
仮に3,000万円を35年ローンで借りた場合、0.2%上乗せで支払総額はおよそ110万円前後増える計算です。
ただし、この金額で「ローン残高をすべて免除できる保障」が得られることを考えると、コストパフォーマンスは高いといえます。
一部の銀行では「金利上乗せなし団信」や、「特約付き団信(がん保障・三大疾病保障など)」を選択できるプランもあります。
また、住宅ローンに比べると投資用ローンはリスクが高いため、団信加入が融資承認の条件となっていることも珍しくありません。
団信の保障内容は、かつての「死亡・高度障害のみ」から大きく進化しています。
いまでは健康リスクに備えたさまざまな特約型が登場しており、ライフステージや健康状態に合わせて選べるようになっています。
代表的なタイプは以下のとおりです。
契約者が「がん」と診断された時点で、ローン残高が全額免除されるタイプ。
治療費や休職リスクに備えられるため、30〜40代の投資家に人気があります。
がん・心筋梗塞・脳卒中の三大疾病が対象。
日本人の死亡原因の上位を占める疾患をカバーできるため、団信の中でも最も一般的な特約です。
三大疾病に加えて、糖尿病・慢性腎不全・高血圧性疾患・肝硬変・慢性膵炎を含む広範囲型。
長期的な通院や休職を伴う生活習慣病にも備えられます。
すべての疾病やケガによる長期入院・就業不能時もカバー。
入院が180日を超えた場合にローン残高を免除するタイプなど、より広いリスクを想定した設計です。
金融機関によって名称や条件は異なりますが、特約が増えるほど金利上乗せ幅(+0.1〜0.3%程度)が拡大します。
そのため、健康状態・職業・家族構成を踏まえて、「どの範囲まで保障が必要か」を慎重に選ぶことが大切です。
たとえば40代男性が、年収700万円・借入額4,000万円・返済期間35年でローンを組む場合。
通常の団信(死亡・高度障害型)のみなら金利2.0%、がん団信付きなら2.2%になるとします。
年換算でおよそ+8万円前後の支出ですが、がんと診断された時点で4,000万円の返済義務が免除されることを考えると、コスト以上の安心を得られることがわかります。
また、団信の保険金には所得税・相続税がかからないため、税務面でも効率的な保障といえます。
団信は、金融と保険の間にある非常にユニークな制度です。
「ローンのリスクヘッジ」と「生命保険としての保障」を同時に果たすこの仕組みは、
不動産投資における“安全装置”であり、“家族への安心の裏付け”でもあります。
ただし、後述するように団信はあくまで「借入残高の返済」に限られるため、
残された家族の生活費や教育費を保障する目的までは担えません。
次章では、生命保険との違いを整理しながら、両者のバランスをどのように取るべきかを解説します。

団体信用生命保険(団信)は、単なる“ローンの付属保険”ではありません。
不動産投資における団信は、資産を守り・家族を残す仕組みとして機能することが最大の魅力です。
ここでは、実際の投資家が感じている3つの主要メリットを、具体的に解説します。
団信の最大のメリットは、契約者に万一があっても家族に「借金のない資産」を残せることです。
一般的な生命保険では、保険金を現金で受け取り、それを生活費や住宅ローン返済に充てます。
一方、団信の場合は、万一のときに保険会社がローン残高を完済してくれるため、
不動産という“形ある資産”がそのまま家族に残ります。
この違いは非常に大きいです。
生命保険の保険金は使えば減っていきますが、不動産は収益を生み続ける可能性があるからです。
たとえば、月8万円の家賃収入があるワンルームマンションを例に考えてみましょう。
契約者が亡くなった場合、団信によりローンは全額完済。
その瞬間から、家賃収入8万円がまるごと家族の純利益になります。
年間で96万円、10年で960万円。
さらに物件を売却すれば、2,000万円〜3,000万円のまとまった資金が入る可能性もあります。
つまり団信は、「死亡時にローンを消す保険」であると同時に、「家族の収入を生み出す装置」にもなり得るのです。
家族にとって、“借金を残さない”という安心だけでなく、“資産を残せる”という希望を持てる──
これが団信付き不動産投資の最も大きな価値です。
団信に加入すると、死亡・高度障害リスクへの備えがすでにカバーされます。
そのため、既存の生命保険を削減・見直しできる可能性があります。
たとえば、生命保険で「死亡保険金3,000万円」の契約をしていた人が、
同額のローン残高を団信でカバーしている場合、
生命保険の保障額を半減しても家族に残る総資産額は変わりません。
結果として、毎月の保険料が数千円〜1万円程度削減できるケースもあります。
年間で数万円、35年間では100万円以上の節約になることも珍しくありません。
特に30〜40代の投資家にとって、保険料の固定費削減は長期的に大きなインパクトを持ちます。
さらに、団信は金利に組み込まれているため、**掛け捨てにならない“保険付きローン”**という位置づけになります。
言い換えれば、「返済を続ける=保障を維持している」状態。
ローン返済が終われば資産が残り、万一のときには保険が機能する──
この両立ができる点で、団信はコストパフォーマンスに優れた保険とも言えます。
ただし、すべてのリスクを団信だけでカバーできるわけではありません。
団信が守るのは“ローン返済”であり、“遺族の生活費”ではありません。
したがって、「生命保険+団信」の組み合わせで全体のリスクバランスを取るのが賢明です。
たとえば、
団信:住宅ローン(3,000万円)を完済するための備え
生命保険:生活費・教育費(2,000万円)を補う備え
といったように目的を分けると、無駄なく安心を確保できます。
もう一つの重要なメリットは、連帯保証人が不要になることです。
団信は、契約者が返済不能になった場合に保険会社が残債を支払うため、金融機関にとっても「貸し倒れリスクを最小化できる」仕組みです。
そのため、団信付きのローンでは、配偶者や親を保証人に立てる必要がないケースがほとんどです。
これにより、家族に保証人としての責任や不安を背負わせることなく、安心して投資を進めることができます。
特に、不動産投資を始めたいけれど「家族に迷惑をかけたくない」という人にとって、団信は精神的な支えになる制度です。
また、金融機関側から見ても、団信加入者は「リスク管理ができている借主」と評価されやすく、結果として融資審査に通りやすくなる傾向もあります。
これは、実際に不動産投資ローンを扱う銀行担当者が明言している点でもあります。

一方で、団信にも「知っておくべきコストと制限」があります。
ここを理解せずに契約すると、後々「思っていた内容と違う」と感じることもあります。
団信の保険料は、ローン金利に含まれているため、保障が厚くなるほど金利が上乗せされる点に注意が必要です。
一般的な上乗せ幅は以下の通りです。
・がん団信:+0.1〜0.2%
・三大疾病団信:+0.2〜0.3%
・八大疾病団信:+0.3〜0.4%
たとえば3,000万円を35年返済で借りる場合、0.3%の上乗せで支払総額は約180万円増加します。
「安心のためのコスト」と割り切れるかが判断の分かれ目です。
団信には健康告知があり、既往症(糖尿病・高血圧・心疾患など)がある場合、加入を断られる可能性があります。
ただし、各銀行では「ワイド団信」や「引受緩和型団信」など、多少の持病でも加入可能な選択肢を用意しています。
金利は通常より+0.2〜0.3%高くなりますが、「加入できない=融資不可」を避けられるメリットは大きいでしょう。
団信はローン期間と連動しているため、途中で解約や内容変更ができません。
たとえば「がん特約を外して保険料を減らしたい」と思っても、原則的にできません。
そのため、最初の契約時に自分の健康・家族構成・将来計画を見据えた上で、「どの特約が本当に必要か」を判断することが何より重要です。
また、ローンを完済すれば団信も自動的に終了するため、“完済後の保障”が必要な人は、別途生命保険や収入保障保険を検討しましょう。
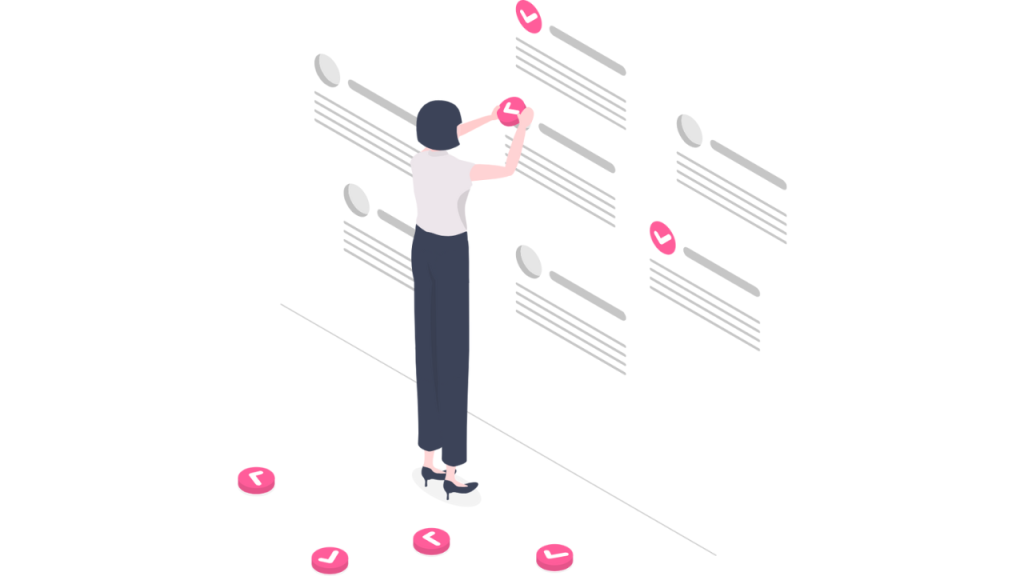
不動産投資ローンに付帯する「団体信用生命保険(団信)」と、一般的な「生命保険」。
どちらも“もしもの時に家族を守る”という点では共通していますが、目的・仕組み・受取人・使い道のすべてが異なります。
これを正しく理解しておくことが、後悔のない資産設計の第一歩です。
両者の違いを一言で表すと、団信は「借金を消すための保険」、生命保険は「生活を守るための保険」です。
団信の保険金は、契約者が死亡または高度障害状態になったとき、金融機関に直接支払われ、そのお金で残りのローンが完済されます。
つまり、団信の目的はあくまで「債務(ローン)」を消すこと。受取人は遺族ではなく、融資を行った銀行です。
一方、生命保険の保険金は遺族が受け取る現金です。
その資金を生活費・教育費・老後資金など、自由に使うことができる点が大きな違いです。
言い換えれば──
・団信:金融機関に支払われ、ローンが帳消しになる
・生命保険:遺族に支払われ、生活資金になる
この仕組みの違いが、“残せるものの質”を大きく左右します。
団信でローンが完済されれば、「借金ゼロ」の状態で不動産が家族に残ります。
しかし、それだけでは生活そのものを支えられない場合も多いのです。
たとえば、夫が投資用マンションを所有し、ローン残高が2,000万円あったとします。
夫の死後、団信で完済され物件が残ったとしても、月の家賃収入が8万円なら年間96万円。
生活費・教育費・住居費をまかなうには到底足りません。
さらに、賃貸経営には以下のようなリスクも伴います。
・空室が続き、家賃収入が途絶える
・修繕・原状回復などの出費が発生する
・管理会社への委託料や固定資産税がかかる
つまり、「不動産が残る=安心」とは限らないのです。
特に、小さな子どもがいる家庭や専業主婦世帯では、家族の生活費を継続的に支えるために生命保険との併用が必要と考えられるでしょう。
団信は“借金を消す保険”であり、生命保険は“生活を支える保険”。
この2つを組み合わせることで、ようやく「経済的にも心理的にも安心できる備え」が成立します。
以下は、40歳男性(年収700万円・妻子あり)が3,000万円の不動産投資ローンを組んだケースです。
| 保険の種類 | 加入内容 | 万一の際の家族の状況 |
|---|---|---|
| 団信のみ | 死亡・高度障害でローン完済 | 不動産は残るが、生活費は家賃収入8万円/月のみ |
| 団信+生命保険(死亡保険2,000万円) | 団信でローン完済+生命保険金を現金で受取 | 不動産+現金2,000万円で、生活・教育費も確保 |
このように、団信単体では「資産」を残せても「生活の持続性」が不足します。
一方、生命保険を併用すれば、“家族の生活と将来”を守る両輪が整うのです。
\オークション査定で投資用マンションをスマート売却/
営業電話に悩まされず、スピーディーに売却を進められます。
「損をせずに手放したい」「売却がなかなか進まない」そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ReTrueへのお問い合わせはこちら最短1分で入力・無料

ここまで見ると、団信はあくまで「ローン返済保険」であり、
生命保険の代替にはならない──という印象を持つかもしれません。
しかし、実際には団信付き不動産投資を「生命保険の代わり」として選ぶ投資家が増えています。
その理由は、“保障+資産形成”という二重のメリットが得られるからです。
生命保険の多くは掛け捨て型で、毎月保険料を支払っても、何事もなく過ごせば手元に残るものはありません。
いわば「安心を買うための支出」であり、資産形成とは切り離された存在です。
それに対して、不動産投資に付帯する団体信用生命保険(団信)は、ローン返済の中に保障が含まれている点が大きな特徴です。
毎月の返済を続けることで、もしもの時には保険として機能し、完済後には現物資産である不動産が確実に手元に残ります。
| 内容 | 支払先 | 結果 |
|---|---|---|
| 生命保険 | 保険会社 | 保障はあるが、資産は残らない(掛け捨て) |
| 団信付きローン | 金融機関+保険組込 | 保障を維持しつつ、不動産という資産が残る |
このように、支払ったお金が“保障”だけで終わるのではなく、“資産”へと変わっていくのが団信付き不動産投資の魅力です。
しかも、保険料分が金利に組み込まれているため、別途の保険料を支払うよりも総コストを抑えられる場合もあります。
団信のもう一つの魅力は、長期的な収入源を作れることです。
ローン完済後の不動産は、家賃収入がそのまま老後の生活資金になります。
たとえば、完済後に月8万円の家賃収入が得られれば、年間96万円。
老後資金が不安な時代において、“第二の年金”として心強い存在です。
この点が、保険との決定的な違いです。
生命保険は一度きりの給付ですが、不動産は継続的にキャッシュフローを生み出します。
それゆえ、「保険+年金+資産形成」を同時に叶えられるのが、不動産投資の強みなのです。
ただし、これは“物件が正しく運営されている”ことが前提です。
立地・管理・修繕計画が甘ければ、空室や家賃下落で収入が減るリスクもあります。
したがって、不動産の選定と管理体制の質が、不動産投資の生命線といえます。
もう一つ、生命保険にはない「団信+不動産投資」の大きな強みが、インフレに対する耐性です。
生命保険で受け取る保険金や、銀行口座に預けた現金は、インフレ(物価上昇)によって実質的な価値が目減りします。
たとえば、今100万円で購入できるものが、将来120万円必要になるとすれば、現金をそのまま持っているだけで購買力は20%失われる計算になります。
一方、不動産は実物資産(リアルアセット)であるため、物価の上昇とともに相対的な価値を保ちやすい性質があります。
特に都市部や需要の高いエリアの物件では、賃料が経済成長や物価上昇に応じて上がる傾向にあります。
つまり、現金が「減っていく資産」だとすれば、不動産は「動きながら守る資産」といえます。
たとえば、今後20年間で物価が20%上昇したと仮定すると、現金の購買力はおよそ8割に下がります。
しかし、入居需要が安定しているエリアの賃貸物件であれば、賃料を同等またはそれ以上の水準で維持できる可能性があります。
結果として、不動産はインフレ局面でも資産価値を保ちながら、継続的な収益を生み出すことができるのです。
さらに、団体信用生命保険(団信)によってローン返済リスクを抑えながら運用すれば、“返済中のリスク管理”と“長期的なインフレ対策”の両方を同時に実現できます。
団信で「守り」を固め、不動産で「価値を育てる」──
これこそが、変動の大きい時代における最も現実的な資産防衛術のひとつです。
生命保険は「お金を残す」手段。
不動産投資は「資産を残す」手段。
どちらも家族を守るための方法ですが、団信付き不動産投資には“自らが築いた資産を形のまま残せる”という強みがあります。
お金は使えば減りますが、不動産は活用次第で収益を生み続けることが可能です。
団信をうまく活用すれば、“守る保険”から“育てる資産”へと発想を変えることができます。
このように、団信と生命保険は似て非なるものです。
どちらが優れているというよりも、目的が異なるため、両方をどう組み合わせるかが重要です。
・団信:借金を消すための保険
・生命保険:生活を守るための保険
・不動産:資産を残すための仕組み
3つをバランスよく設計することで、はじめて「守りながら増やす資産戦略」が完成します。

団体信用生命保険(団信)を活用すれば、もしもの時にローンが完済され、不動産という“形ある資産”を残すことができます。
ただし、不動産投資で考えるべきリスクは「万一」だけではありません。
実際には、オーナーが生きている間に起こり得る現実的なリスクのほうが多く、これをどう管理するかが長期的な資産防衛のカギになります。
ここでは、不動産投資に伴う主なリスクと、それぞれに対応する保険・対策を整理してみましょう。
立地や築年数に関係なく、どんな物件にも空室リスクは存在します。
入居者がいなければ家賃収入はゼロ。ローン返済や管理費の支払いが滞り、キャッシュフローは一気に悪化します。
特に単身者向けワンルームは入退去が頻繁で、平均入居期間はおよそ2〜3年。
退去ごとに1〜2か月空くと、年間利回りに大きく影響します。
・サブリース契約(家賃保証)を利用し、空室時も一定収入を確保する
・立地・交通利便性・築年数の条件が良い物件を選ぶ
・家賃補償保険に加入し、想定外の空室損失を軽減する
ただし、サブリース契約は家賃が2〜3割下がるケースもあるため、収支バランスを慎重に検討することが必要です。
不動産は「時間の経過」とともに必ず劣化します。
給湯器やエアコンの交換、配管の修理などは避けられず、突発的な出費になることも。
築15年を過ぎると、外壁塗装や防水工事などの大規模修繕も必要になります。
修繕積立金だけでは賄いきれず、オーナー負担が発生する場合もあります。
・年間10〜15万円程度を修繕予備費として確保する
・設備延長保証サービス(家主向け)を活用する
・中古物件の場合は、購入前に管理会社の修繕履歴を確認する
賃貸市場は常に動いており、エリアの競争や築年数の経過で家賃が下がることもあります。
また、周辺に新築物件が増えると、築古マンションの入居率は低下しがちです。
資産価値も同様で、築年数が進むにつれて売却価格が下がる傾向にあります。
不動産投資では、家賃収入(インカムゲイン)と売却益(キャピタルゲイン)の両方を見据える必要があります
・再開発や人口増加が見込まれるエリアを選ぶ
・定期的に賃料を見直し、必要に応じてリフォーム投資を行う
・「売り時」を想定した出口戦略をあらかじめ設計しておく
地震・台風・火災などの自然災害は、立地が良くても避けることはできません。
被害が発生すれば、修繕費や一時的な家賃損失が生じます。
・火災保険・地震保険への加入は必須
・「家賃損失補償特約」を付けて、被災時の収入減を補う
・ハザードマップを確認し、リスクの低い立地を選ぶ
火災保険料は年々上昇しており、2025年以降も引き上げが見込まれます。
特に沿岸部や低地の物件では保険料が高くなるため、保険料と立地リスクをセットで検討することが重要です。
団信は金利に上乗せされる仕組みですが、そもそもの金利自体が上昇すると返済負担が増えます。
変動金利で借入している場合、金利上昇が続けば月々の返済額が数万円単位で増える可能性もあります。
・固定金利型ローンを選び、返済額を安定させる
・低金利のうちに借換(リファイナンス)を検討する
・家賃収入の一部を貯蓄し、金利上昇に備える
管理会社の対応次第で、物件の稼働率や資産価値は大きく変わります。
入居者とのトラブル対応や滞納処理を怠る管理会社を選んでしまうと、オーナーが損失を被るケースもあります。
・管理実績があり、対応スピードの早い会社を選ぶ
・修繕・原状回復費用の基準を事前に確認する
・定期的に管理報告書をチェックし、疑問点を放置しない
信頼できる管理会社は、物件を「守るパートナー」です。
収益性だけでなく、管理体制の質が不動産投資の安定性を左右します。
税制改正や法律の見直しは、不動産オーナーの利益に直結します。
固定資産税の評価額上昇や、住宅ローン控除の縮小などはその一例です。
相続税や譲渡所得に関する特例も、数年ごとに条件が変更される可能性があります。
・最新の税制改正情報を定期的にチェックする
・売却・相続を見据え、税理士や不動産会社と連携する
・定期的に資産全体を見直し、リスク分散を図る
不動産投資は、「家賃収入でローンを返す」という単純な構図ではありません。
実際は、金利・修繕・空室・税制・災害・健康といった多様なリスクが絡み合います。
だからこそ、それぞれの保険の役割を整理して併用することが重要です。
| 保険の種類 | 補償対象 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 団信 | 契約者の死亡・高度障害 | ローン残高の完済 |
| 生命保険 | 遺族の生活費・教育費 | 生活保障 |
| 火災・地震保険 | 建物損壊・家賃損失 | 物的リスクの補償 |
| 家賃補償保険 | 空室・滞納リスク | 収益安定化 |
投資はリターンを追うだけでなく、「守り方」を設計することが成功の条件です。
団信でローンリスクを抑え、火災保険で建物を守り、生命保険で家族を支える。
複数の保険をうまく組み合わせることが、結果的に最も効率のよい“リスクマネジメント投資”につながります。

団団体信用生命保険(団信)は、不動産投資における“借金を消す保険”として非常に有効です。
万一の際にもローンが完済され、家族には負債のない不動産資産が残ります。
ただし、団信はあくまで「ローン返済を守る」ための仕組みであり、
遺族の生活費や教育費といった“日々の暮らし”までは補うことができません。
本当に安心できる資産設計とは、
といった多層的なリスクマネジメントを組み合わせることにあります。
不動産投資の本質は、“守りながら増やす”こと。
もしもの時にも備えながら、家族の未来に残る資産を育てていく。
それこそが、団信を活かした賢く持続的な投資の形といえるでしょう。
\オークション査定で高値売却を実現/
複数の不動産会社が同時に入札する「オークション形式」で、最も高い査定を提示した会社をご紹介します。営業電話もなく、スムーズに比較検討できる安心の仕組みです。
「損をせずに手放したい」「信頼できる会社に任せたい」という方は、まずは無料査定からお試しください。
ReTrueの無料査定を試す